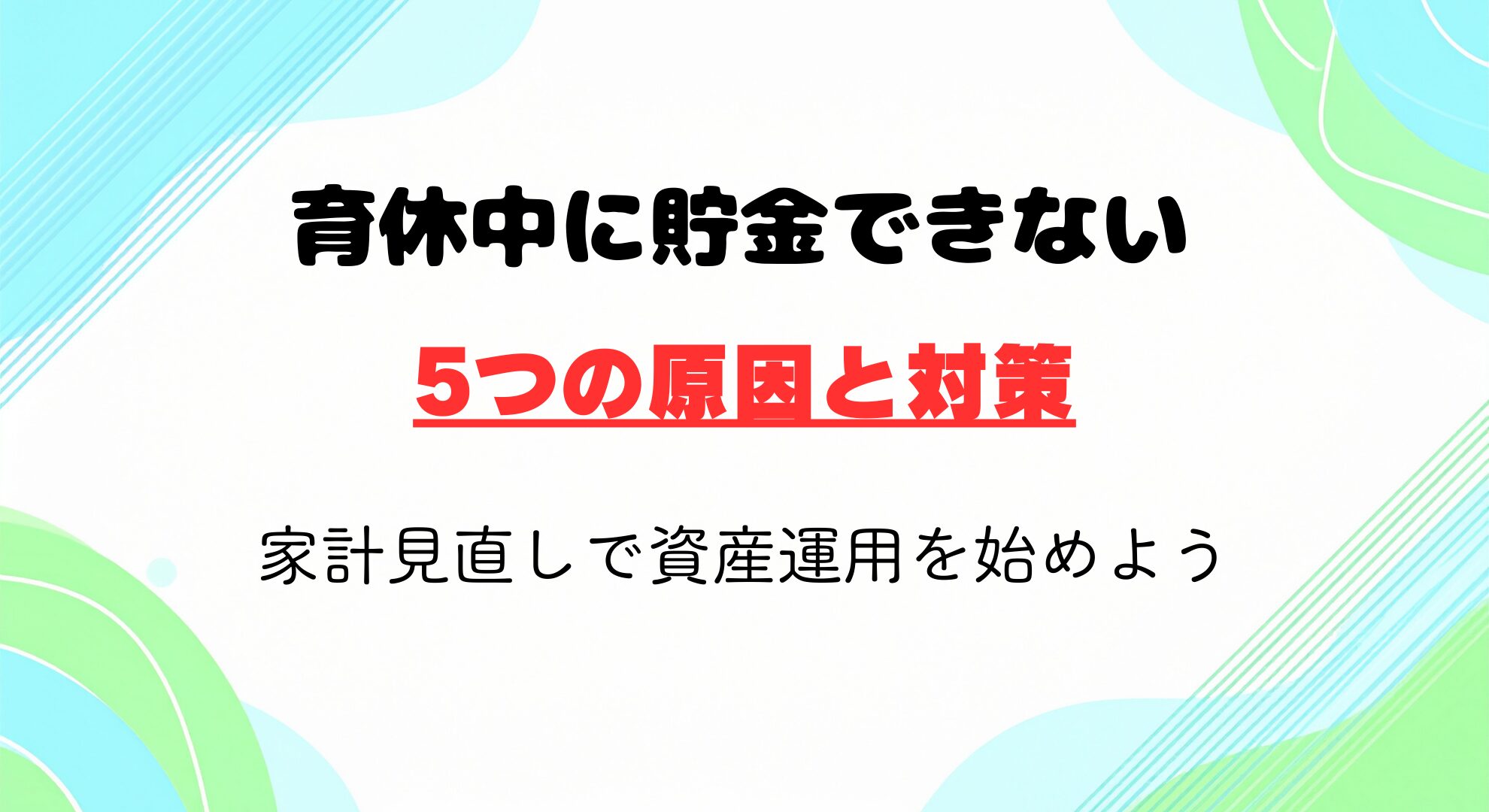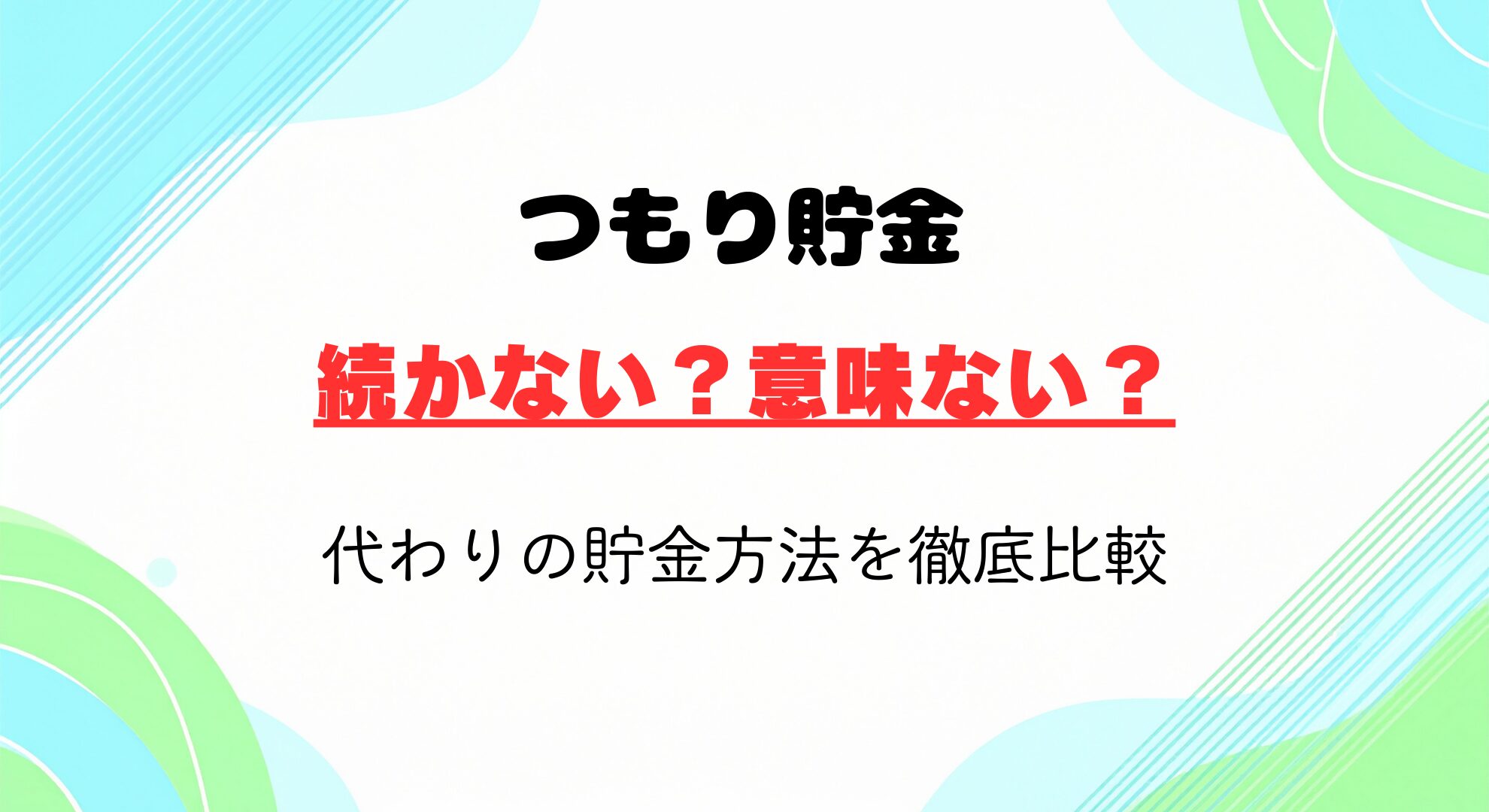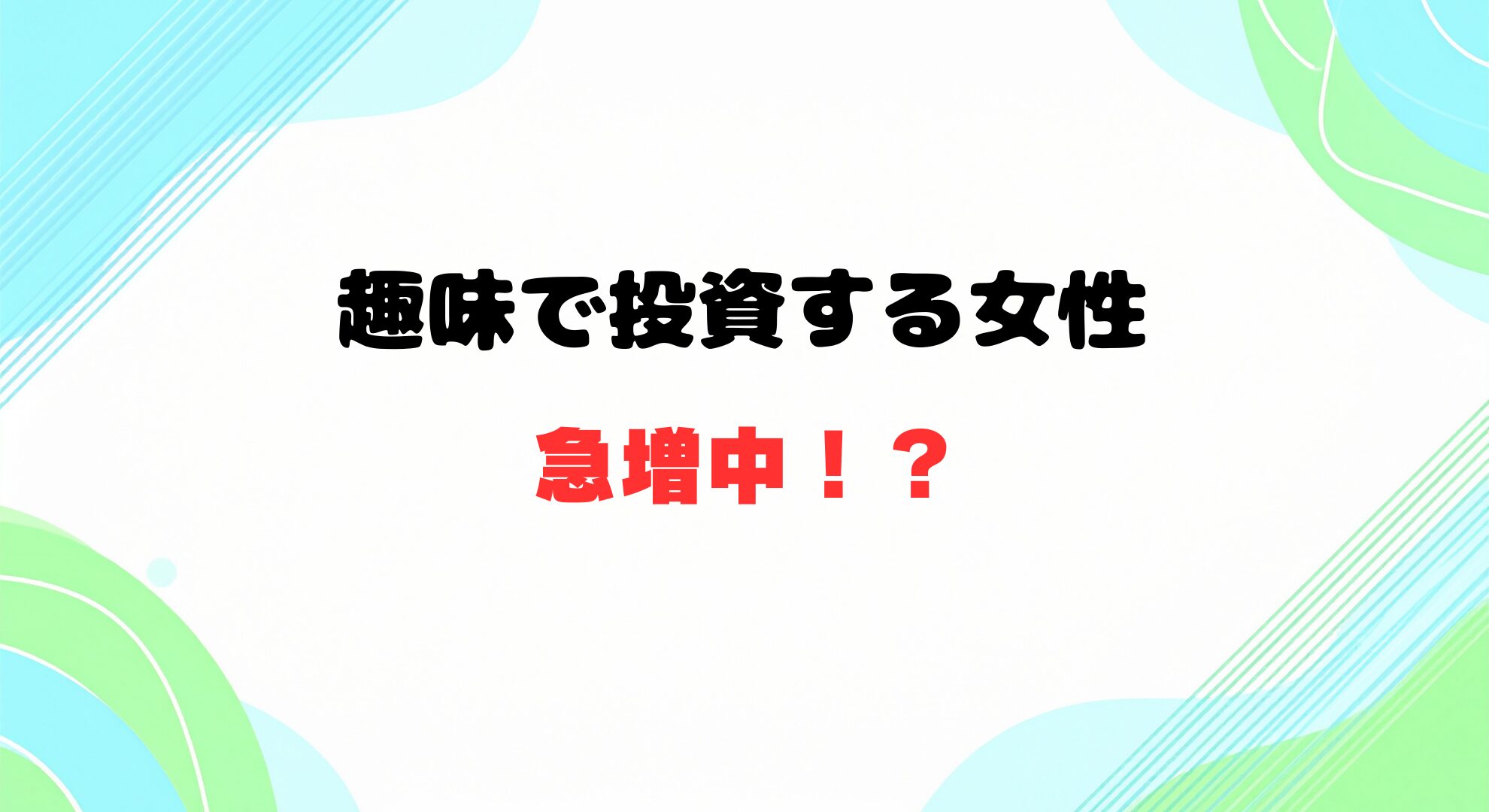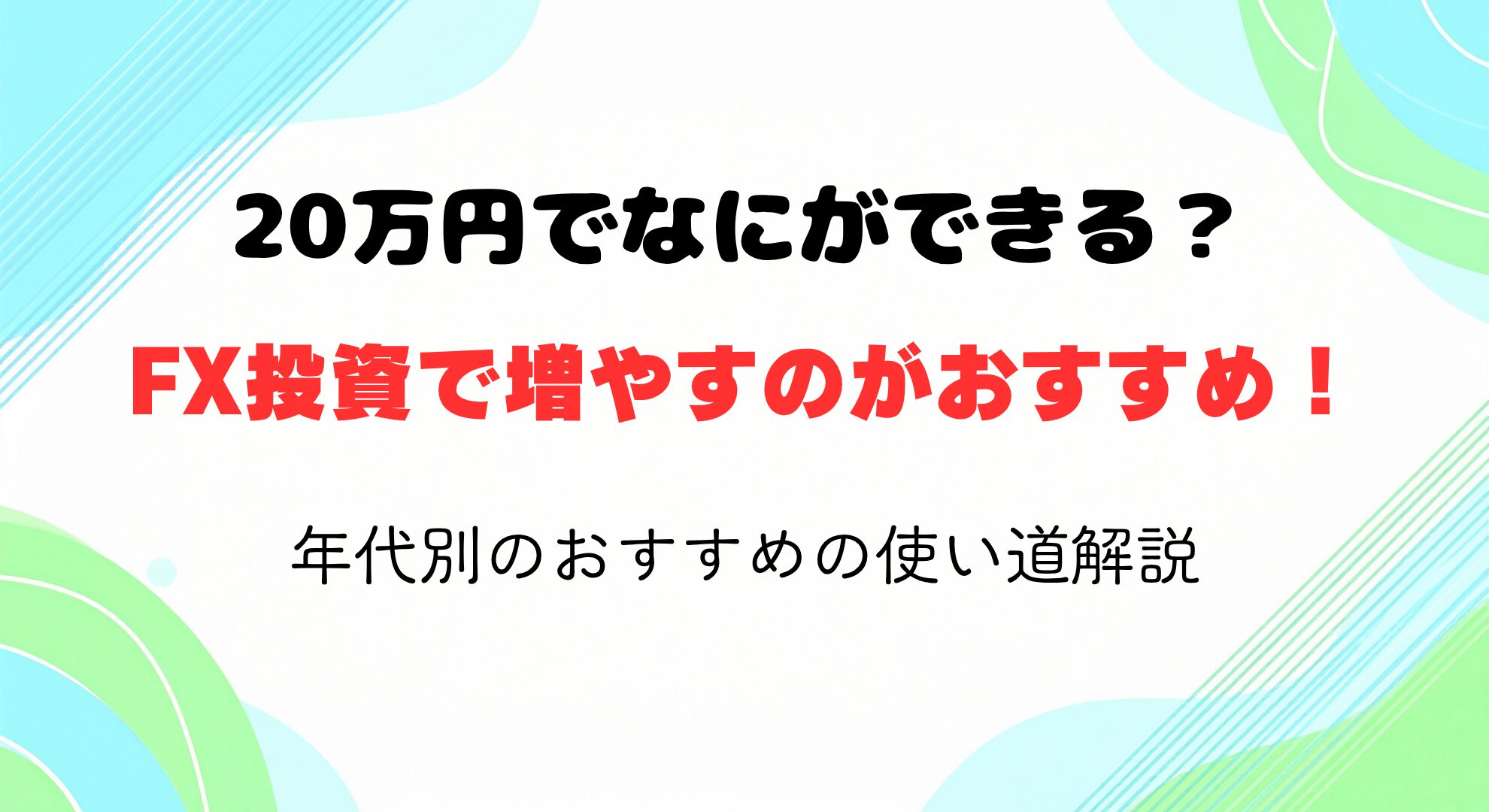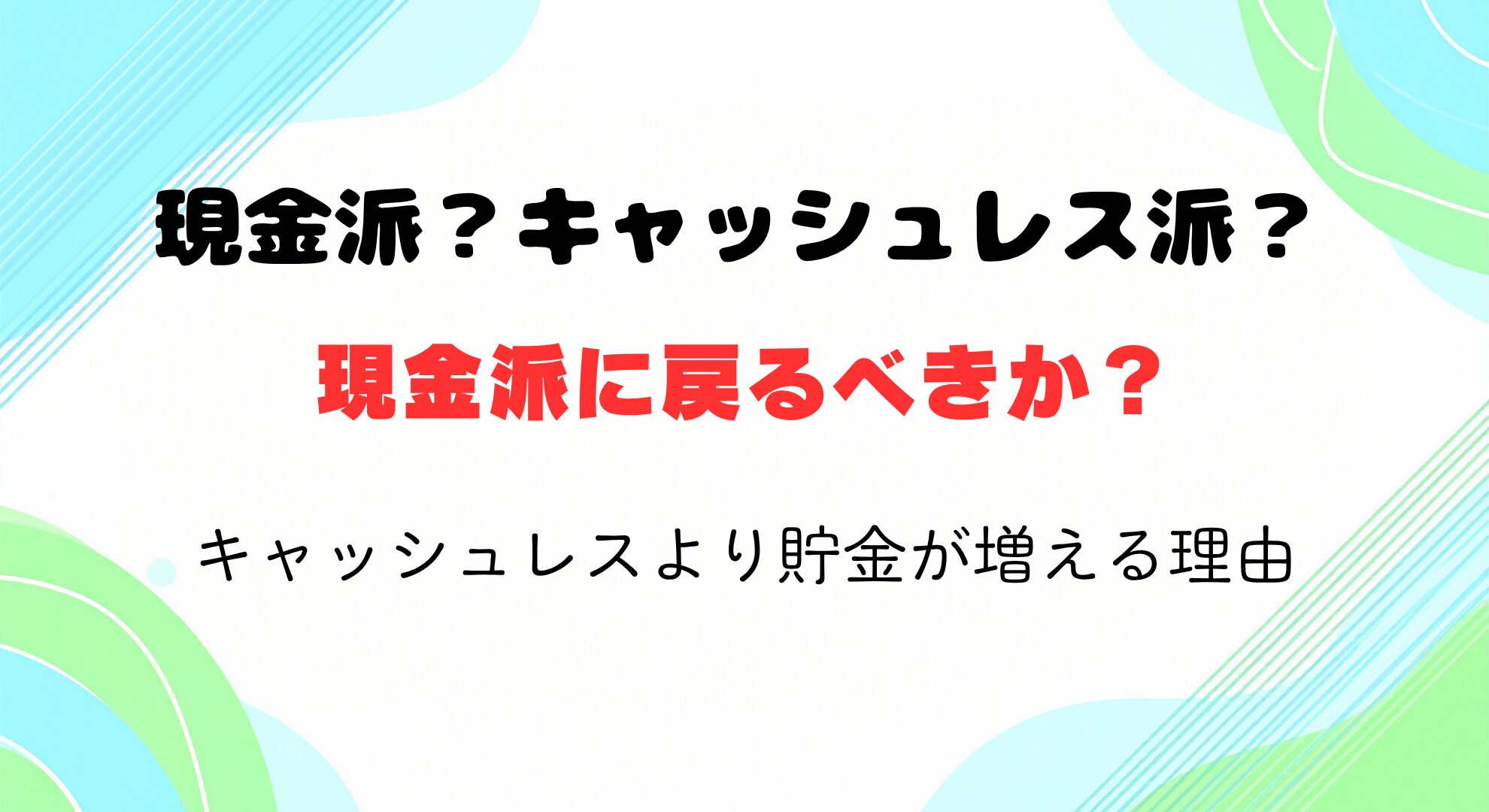この記事では、育休中に貯金ができないと悩むあなたのために、具体的な原因と今すぐできる解決策を徹底解説します。
育休に入って収入は減るのに、おむつ代や光熱費など子育ての支出は増える一方で、家計が苦しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
結論、育休中に貯金ができない悩みは、家計の「固定費」を見直し、スキマ時間で「月1万円」の収入を増やすことで解決できます。
貯金できなくて当たり前、と悩む必要はありません。
この記事で紹介する方法を実践すれば、家計に余裕が生まれるだけでなく、そのお金を元手に資産運用を始め、将来のお金の不安を解消する第一歩を踏み出せますよ。
この記事でわかること
- 育休中に貯金できない根本的な原因
- 今すぐできる固定費の具体的な節約術
- 育児中でも無理なく月1万円稼ぐ方法
- 節約で生まれたお金を将来のために増やす資産運用の始め方
目次
結論|育休中に貯金できない悩みは家計の見直しと月1万円の収入増で解決できる!

育休中に思うように貯金ができず、焦りや不安を感じてしまうのは、あなただけではありません。
実際、多くのご家庭が収入の減少と育児関連の支出増に直面し、これまでのようにお金を貯められなくなるのは、ある意味で当然のことです。
この状況を乗り越える鍵は、まず家計の固定費を徹底的に見直し、同時に育児のスキマ時間を活用して月1万円でも収入を増やすことです。
そうして生み出した余裕資金を、将来のために賢く運用していくことで、育休中を「お金の不安を解消し、資産を増やす準備期間」に変えることができますよ。
育休中の貯金できない悩みを解決する3ステップ
- 貯金できなくて当たり前!まずは家計の現状把握と固定費削減から
- 節約とポイ活・副業で月3万円の余裕資金を作り将来のための資産運用に回す
- 夫婦で家計状況を共有し協力体制を築くことが貯金できない状況を脱する鍵
貯金できなくて当たり前!まずは家計の現状把握と固定費削減から
「子どもが生まれる前は貯金できていたのに…」と自分を責める必要は全くありません。
育休中は収入が減り、逆に出費が増えるのですから、貯金ができなくなるのは仕方のないことです。
大切なのは、この現実を受け入れた上で、具体的な一歩を踏み出すこと。
まずは家計簿アプリなどを活用して、毎月何にいくら使っているのかを「見える化」し、家計の現状を正確に把握しましょう。
その上で、最も効果が高く、かつ一度手をつければ節約効果がずっと続く固定費の削減から始めるのが、家計改善の鉄則です。
節約とポイ活・副業で月3万円の余裕資金を作り将来のための資産運用に回す
家計の現状を把握し、固定費を削減するだけでも手元に残るお金は増えますが、さらに「ポイ活」や「在宅ワーク」で収入を増やす意識を持つと、家計は一気に楽になります。
目標は、節約と収入増を合わせて月3万円の余裕資金を作ること。
この月3万円は、単に生活費の足しにするのではありません。
将来の教育費や老後資金といった、漠然としたお金の不安を解消するための資産運用の原資にしましょう。
育休中に資産運用の第一歩を踏み出せば、復職後にはさらに大きな金額を投資に回せるようになり、将来のお金の心配を大きく減らすことができるでしょう。
夫婦で家計状況を共有し協力体制を築くことが貯金できない状況を脱する鍵

育休中のお金の悩みは、決して一人で抱え込むべきではありません。
「夫は楽観的で、危機感を共有してくれない」と感じるかもしれませんが、それは夫が家計のリアルな状況を知らないだけ、というケースがほとんどです。
家計簿アプリなどで「見える化」した収支状況を夫婦で共有し、「このままだと、将来のために貯めたいお金が貯められないね」と冷静に事実を伝えましょう。
感情的にならずに具体的な数字を見せることで、夫も当事者意識を持ってくれるはずです。
家計という共通の目標に向かって夫婦で協力体制を築くことこそ、育休中の金銭的な不安、そして精神的なストレスを乗り越えるための最も重要な鍵となります。
6割以上が実感!育休中に貯金できない3つの原因と乗り越え方

「育休に入ってから、全く貯金ができない…」と悩んでいるのは、決してあなた一人ではありません。
株式会社ビズヒッツの調査では、育休経験のある女性の6割以上が「育休中に旦那様の給料だけでは足りなかった」と回答しています。
多くの家庭が同じ壁にぶつかっているのです。
では、なぜ育休中はこれほどまでに貯金が難しくなるのでしょうか。
ここでは、その主な3つの原因と、それぞれの乗り越え方のヒントを見ていきましょう。
育休中に貯金ができない3つの原因
- 育児休業給付金だけでは足りない!共働き時代からの世帯収入ダウン
- おむつ代・光熱費・イベント費用など子育て世帯特有の支出増
- 家計管理が後回しになりがちで「どんぶり勘定」に陥ってしまう
育児休業給付金だけでは足りない!共働き時代からの世帯収入ダウン
育休中にお金の不安を感じる最大の原因は、やはり収入の減少です。
育休中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、その金額は休業開始前の給料と比べて少なくなります。
具体的には、育休開始から180日目までは休業前賃金の約67%、181日目以降は50%が支給額の目安です。
これまで共働きで家計を支えていた場合、片方の収入が半減、あるいはそれ以下になるわけですから、家計が苦しくなるのは当然でしょう。
さらに、育児休業給付金は毎月ではなく「2ヶ月に1回」まとめて振り込まれるため、日々の資金繰りが難しく感じる一因にもなっていますね。
おむつ代・光熱費・イベント費用など子育て世帯特有の支出増
収入が減る一方で、子どもが生まれたことで新たな支出が次々と発生します。
毎日消費するおむつやミルク代はもちろん、ベビーカーやベビー服、チャイルドシートといった育児グッズの購入も必要です。
また、赤ちゃんがいると家にいる時間が増え、冷暖房を常に稼働させたり、洗濯の回数が増えたりするため、水道光熱費も確実に上がります。
お宮参りやお食い初めといった行事、記念の写真撮影など、嬉しいイベントにも何かとお金がかかるものです。
こうした「子育て特有の支出」が積み重なり、思った以上に家計を圧迫することが、貯金できない大きな要因となっています。
家計管理が後回しになりがちで「どんぶり勘定」に陥ってしまう
育休中は、赤ちゃんの世話に追われ、時間的にも精神的にも全く余裕がありません。
そのため、これまで家計簿をつけていた人でも、レシートを整理したり、支出を記録したりする作業が後回しになりがちです。
結果として、何にいくら使ったのかを正確に把握できない「どんぶり勘定」に陥り、「気づいたらお金がなくなっていた」という事態を招きます。
このような状況は、お金の不安を増大させるだけでなく、「自分は節約しているのに、夫は無駄遣いしている」といった夫婦間のすれ違いやストレスの原因にもなります。
家計管理が疎かになることも、貯金を難しくする隠れた要因と言えるでしょう。
育休中に貯金できない状況を脱出する家計見直し術|まず固定費をとことん節約

「収入が減って支出が増えるなら、節約するしかない」と考えたとき、最も効果的で、かつ優先して取り組むべきなのが固定費の見直しです。
食費などの変動費を切り詰める節約は日々の努力が必要でストレスも溜まりがちですが、固定費は一度見直してしまえば、その後は何もしなくても毎月ずっと節約効果が続きます。
時間に比較的余裕のある育休中は、面倒に感じて後回しにしてきた固定費に手をつける絶好のチャンスですよ。
今すぐ見直すべき固定費リスト
- スマホを格安SIMに乗り換えて通信費を月5,000円以上安くする
- 家のネット回線や電気・ガス会社の見直しで年間数万円を節約
- 生命保険の見直しで保険料を最適化!FPへの無料相談も活用
- 食費や日用品費はふるさと納税やポイント・クーポン活用で無理なく削減
スマホを格安SIMに乗り換えて通信費を月5,000円以上安くする
家計の固定費で最も手軽に、かつ大幅に削減できるのがスマホの通信費です。
もし今、夫婦でドコモ・au・ソフトバンクといった大手キャリアを使っているなら、楽天モバイルやワイモバイルなどの格安SIMに乗り換えるだけで、通信費を劇的に安くできます。
例えば、夫婦2人で大手キャリアの無制限プランを使い、月に合計15,000円ほど支払っている場合を考えてみましょう。
楽天モバイルならデータ無制限で月額3,278円、ワイモバイルなら30GBで月額2,178円(割引適用時)から利用可能です。
夫婦で乗り換えれば、毎月5,000円以上、年間で60,000円以上の節約になる計算です。
浮いたお金をそのまま貯金や投資に回せるわけですから、やらない手はありませんね。
家のネット回線や電気・ガス会社の見直しで年間数万円を節約
スマホと合わせて見直したいのが、自宅のインターネット回線です。
特に大手キャリアの光回線(ドコモ光やソフトバンク光など)を契約している場合、月額料金が安い「おてがる光」などに乗り換えるだけで、年間1万円以上の節約が可能です。
また、赤ちゃんがいると増えがちな電気代も、電力会社・ガス会社を切り替えることで安くできます。
今はネットで簡単に料金シミュレーションができるので、どのくらい安くなるかチェックしてみるのがおすすめです。
これらの手続きは少し面倒に感じるかもしれませんが、一度やってしまえば効果は大きいですよ。
生命保険の見直しで保険料を最適化!FPへの無料相談も活用
子どもが生まれたことをきっかけに、生命保険の見直しを検討することも非常に重要です。
独身時代や夫婦二人だけの時に加入した保険は、現在の家族構成に対して保障が過剰だったり、逆に不足していたりするケースが少なくありません。
特に、毎月数万円もの保険料を支払っている場合は、保障内容を今のライフステージに合わせて最適化することで、保険料を大幅に削減できます。
とはいえ、保険の専門知識がないと、どの保険を選べばいいか分からないでしょう。
そんな時は、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。
最近は無料で家計全体の相談に乗ってくれるサービスも多いので、一度活用してみる価値は十分にあります。
食費や日用品費はふるさと納税やポイント・クーポン活用で無理なく削減
食費や日用品費といった変動費は、無理に切り詰めるとストレスの原因になります。
特に、産後のママの栄養や、育児の息抜きとなるささやかな贅沢まで削ってしまうのは避けたいところです。
変動費の節約は、「我慢」ではなく「工夫」で乗り切りましょう。
例えば、お米やお肉といった食料品は「ふるさと納税」の返礼品で手に入れれば、実質2,000円の負担で済みます。
おむつやミルクなどのベビー用品は、楽天やAmazonのセール、ポイントアップデーを狙ってまとめ買いするのがお得です。
普段の買い物も、ポイントサイトを経由したり、キャッシュレス決済のクーポンを使ったりするだけで、支出を無理なく抑えることができますよ。
育休中に貯金できないなら月1万円の収入増を目指す!おすすめ副業・ポイ活

固定費の見直しで支出を減らす「守りの家計改善」と同時に、少しでも収入を増やす「攻めの家計改善」にもチャレンジしてみましょう。
「育児で忙しいのに、働くなんて無理」と感じるかもしれませんが、今はスマホ一つで、育児や家事のスキマ時間にできるお仕事がたくさんあります。
目標はまず月1万円の収入増です。
毎月1万円でも収入が増えれば、家計のやりくりは格段に楽になり、精神的な余裕も生まれます。
ここでは、育休中のママでも無理なく始められる方法を3つ紹介しますね。
育休中でもできる収入アップ術
- スキマ時間でOK!アンケートモニターやポイ活で月5,000円稼ぐ
- フリマアプリで不用品を売ってまず1万円の臨時収入を得る
- クラウドソーシングの在宅ワークで月1〜3万円の安定収入を目指す
スキマ時間でOK!アンケートモニターやポイ活で月5,000円稼ぐ
最も手軽に始められるのが、アンケートモニターやポイントサイトを活用した「ポイ活」です。
スマホアプリやウェブサイトに登録し、送られてくる簡単なアンケートに答えたり、指定されたサービスを利用したりするだけで、現金や電子マネーに交換できるポイントが貯まります。
赤ちゃんがお昼寝している時間や、夜寝かしつけた後のちょっとした時間を使ってコツコツ続けるだけで、月に数千円程度なら十分に稼ぐことが可能です。
大きな金額にはなりませんが、おむつ代や自分のささやかなお小遣いを稼ぐにはぴったりの方法でしょう。
ポイントサイトを経由してネットショッピングするだけでもポイントが貯まるのでおすすめです。
フリマアプリで不用品を売ってまず1万円の臨時収入を得る
子どもが生まれると、家の中はあっという間にモノで溢れかえります。
もう着られなくなったマタニティウェアや、サイズアウトしたベビー服、使わなかった育児グッズなどは、メルカリなどのフリマアプリで売ってしまいましょう。
家の整理整頓ができてスッキリする上に、まとまった臨時収入を得ることができます。
出品作業は、スマホで写真を撮って説明文を書くだけなので、意外と簡単です。
最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度やり方を覚えてしまえばスムーズにできますよ。
まずは家の中を見渡して、「これは売れるかも」というものを探すところから始めてみてください。
クラウドソーシングの在宅ワークで月1〜3万円の安定収入を目指す
もう少し安定した収入を目指したいなら、クラウドソーシングサイトに登録して在宅ワークに挑戦するのも一つの手です。
クラウドソーシングサイトとは、仕事を依頼したい企業と、仕事を受けたい個人を繋いでくれるプラットフォームのこと。
簡単なデータ入力や文字起こし、アンケートの集計、体験談のライティングなど、特別なスキルがなくても始められる仕事がたくさん募集されています。
自分のペースで仕事量や時間を調整できるので、育児との両立もしやすいのが大きなメリットです。
最初は単価が低いかもしれませんが、実績を積むことで、月1〜3万円、あるいはそれ以上の収入を得ることも夢ではありません。
育休中に副業をする際は、念のため会社の就業規則を確認しておきましょう。
育休中に貯金できない人が見落としがちな公的制度|申請で手元資金を増やす

家計の見直しや収入アップの努力と並行して、絶対に忘れてはならないのが公的制度の活用です。
日本には、子育て世帯を支援するための様々な制度がありますが、その多くは自分で申請しないと利用できません。
つまり、知っているか知らないか、行動するかしないかで、受け取れるお金に数万円、場合によっては数十万円もの差が出てしまうのです。
ここでは、育休中のママが必ずチェックしておくべき4つの重要な制度について解説します。
「知らなかった」で損をしないよう、しっかり確認してくださいね。
必ず確認!育休中に使える公的制度
- 育児休業給付金の支給額とタイミングを正確に把握する
- 社会保険料の免除手続きは完了済みか必ず確認しよう
- 児童手当は絶対に使わない!将来の教育費として別口座で貯蓄する
- 出産・育児でかかった医療費は高額療養費制度や医療費控除で取り戻す
育児休業給付金の支給額とタイミングを正確に把握する
育休中の貴重な収入源である「育児休業給付金」。
まずは、育児休業給付金の支給額と支給タイミングを正確に把握しておくことが家計管理の第一歩です。
前述の通り、支給額は育休開始から180日までは休業前賃金の約67%、それ以降は50%が目安となります。
また、支給は2ヶ月に1回なので、そのサイクルを前提とした資金計画を立てる必要があります。
会社から受け取る給与明細や支給決定通知書などで、自分の支給額がいくらなのか、次の振込はいつなのかを必ず確認し、夫婦で共有しておきましょう。
社会保険料の免除手続きは完了済みか必ず確認しよう
育休中は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料の支払いが、本人負担分も会社負担分も全額免除されます。
これは家計にとって非常に大きなメリットですが、免除を受けるためには会社が年金事務所などへ申し出る必要があります。
基本的には会社が手続きを行ってくれますが、万が一漏れがあると大変です。
給与明細を見て、社会保険料が天引きされていないかを必ず確認してください。
もし引かれている場合は、すぐに会社の担当部署に問い合わせましょう。
社会保険料が免除されても、将来受け取る年金額が減ることはないので安心してくださいね。
児童手当は絶対に使わない!将来の教育費として別口座で貯蓄する
子どもが生まれれば、中学校卒業まで「児童手当」が支給されます(所得制限あり)。
3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円(第3子以降は増額)と、決して少なくない金額です。
家計が苦しいと、児童手当をつい生活費の足しにしたくなりますが、それは絶対に避けましょう。
児童手当は、「子どもの将来のための資金」として、生活費の口座とは別の専用口座で貯蓄するのが鉄則です。
このルールを徹底するだけで、子どもが15歳になる頃には約200万円もの教育資金が自動的に貯まる計算になります。
将来の大きな安心に繋がるので、ぜひ実践してください。
出産・育児でかかった医療費は高額療養費制度や医療費控除で取り戻す
出産は病気ではないため健康保険は適用されませんが、帝王切開での出産や切迫早産での入院など、医療行為が発生した場合は保険適用となります。
その際、1ヶ月の医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」を利用することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
また、出産費用が出産育児一時金(原則50万円)を上回った場合の自己負担分や、妊娠中の定期健診費用、通院のための交通費などは「医療費控除」の対象です。
家族全員で年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得税や住民税が還付されます。
申請しないと戻ってこないお金なので、忘れずに手続きしましょう。
育休中に貯金できない状況から脱却!節約で浮いたお金で資産運用を始める

ここまで解説してきた「支出の削減」と「収入の増加」を実践すれば、あなたの家計には毎月1万円、多ければ3万円以上の余裕資金が生まれるはずです。
この大切なお金を、ただ銀行に預けておくだけで満足してはいけません。
育休中という時間を、目先のやりくりだけでなく、将来のお金の不安を根本から解消するための資産運用の準備期間と捉え、新たな一歩を踏み出しましょう。
お金に働いてもらう仕組みを作ることで、あなたの将来はもっと豊かになりますよ。
育休後を見据えた資産形成プラン
- 節約・副業で生まれた月3万円を投資の原資にしてお金に働いてもらう
- DMM FX|攻めの資産運用でお金を増やす
- 新NISAで教育費や老後資金を非課税で効率的に準備する
節約・副業で生まれた月3万円を投資の原資にしてお金に働いてもらう
節約や副業で生み出した月3万円は、いわば「なかったものとして扱えるお金」です。
このお金を投資の原資にすることで、精神的な負担も少なく資産運用をスタートできます。
現在の超低金利時代では、銀行に預けておくだけではお金はほとんど増えませんし、むしろ物価上昇(インフレ)によって、現金の価値は年々目減りしていくリスクさえあります。
だからこそ、余裕資金を株式や投資信託、FXといった金融商品に換えて「お金自身に働いてもらう」という発想が不可欠なのです。
育休中に少額からでも投資を始めることで、お金が増える仕組みを体感し、復職後の本格的な資産形成に繋げていきましょう。
DMM FX|攻めの資産運用でお金を増やす

「投資」と聞くと、まとまった資金が必要だったり、専門知識がないと難しかったりするイメージがあるかもしれません。
しかし、FX(外国為替証拠金取引)なら、レバレッジを効かせることで少ない資金でも大きな取引ができ、円安や円高といった為替の動きを利益に変えるチャンスがあります。
特におすすめなのが、初心者でも使いやすいと評判の「DMM FX」です。
DMM FXは、直感的に操作できるスマホアプリや、24時間対応のLINEサポートなど、FXが初めての方でも安心して始められる環境が整っています。
最近では、AIに過去のデータを分析させて値動きを予測できるので、専門家でなくても負けにくい運用ができます。
いつ買って、いつ売るかをあらかじめ決めておくことで、感情に流されない冷静な取引がしやすくなります。
節約で生まれた余裕資金の中から、まずは1万円、3万円といった少額で、攻めの資産運用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
新NISAで教育費や老後資金を非課税で効率的に準備する
FXのような短期的な利益を狙う「攻めの投資」と並行して、将来のための資金をコツコツと育てる「守りの投資」も始めましょう。
そのための最適な制度が、2024年から始まった新しい「NISA(少額投資非課税制度)」です。
新NISAは、年間最大360万円までの投資で得た利益が非課税になるという、国が用意してくれた非常にお得な制度です。
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、新NISA口座内での取引なら、その税金が一切かかりません。
毎月1万円、3万円といった金額を、全世界の株式に分散投資する投資信託(例えばS&P500など)で積み立てていけば、子どもの大学進学費用や、自分たちの老後資金といった長期的な目標に向けた資産を、効率的に準備することができますよ。
育休中に貯金できないことに関してよくある質問

最後に、育休中に貯金できないことに関してよくある質問に回答します。
よくある質問
- 育休に入る前に、貯金はいくらあると安心ですか?
- 育休中、本当にお金が足りなくて生活が苦しい時はどうすればいいですか?
- 手取り20万円の場合、育児休業給付金はいくらもらえますか?
- 育児休業給付金がもらえない(0円になる)のはどんな場合ですか?
- 育休中の手取りが10割(8割)になる制度改正はいつからですか?
- 育休中に支払いが免除されるものは何ですか?
- 夫(パパ)が育休を取った場合も給料は減りますか?
育休に入る前に、貯金はいくらあると安心ですか?
最低でも生活費の半年分、できれば1年分の貯金があると安心です。
会社員など比較的収入が安定している場合は半年分、自営業などで収入が不安定な場合は1年分が「生活防衛費」の一つの目安となります。
育児休業給付金は支給までに時間がかかる場合や、急な病気・ケガなど不測の事態にも対応できるため、ある程度まとまった貯金があると精神的な余裕が生まれますよ。
育休中、本当にお金が足りなくて生活が苦しい時はどうすればいいですか?
まずは本文で紹介した固定費の見直しを最優先で実行し、それでも厳しい場合は公的な貸付制度の利用を検討しましょう。
安易にカードローンや消費者金融に頼るのではなく、お住まいの市区町村にある社会福祉協議会が窓口となっている「生活福祉資金貸付制度」など、セーフティネットとして用意されている制度に相談するのがおすすめです。
もちろん、頼れるのであれば両親や親族に一時的に援助をお願いするのも一つの方法です。
手取り20万円の場合、育児休業給付金はいくらもらえますか?
最初の半年間は月額 約15万円、それ以降は月額 約11万円が目安です。
育児休業給付金は税金のかからない手取り額ではなく、社会保険料などが引かれる前の「額面給与」を元に計算されます。
手取り20万円の場合、額面給与を約22万円と仮定すると、最初の180日間は月額147,400円(22万円×67%)、181日目以降は月額110,000円(22万円×50%)が支給される計算になります。
育児休業給付金がもらえない(0円になる)のはどんな場合ですか?
育休に入る前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月未満の場合などが該当します。
例えば、転職したばかりで雇用保険の加入期間が短い場合や、自営業・フリーランスで雇用保険自体に加入していない場合は、給付金の支給対象外です。
また、育休中に会社から給料の8割以上が支払われている場合や、副業などで働きすぎて一定の条件を超えた場合も、支給が停止されるため注意が必要です。
育休中の手取りが10割(8割)になる制度改正はいつからですか?
2025年4月1日から、新しい制度が施行される予定です。
この制度は「産後パパ育休」の給付率を引き上げるもので、両親ともに14日以上の育休を取得するなど、一定の条件を満たした場合に適用されます。
条件を満たすと、最大28日間、休業前賃金の80%相当の給付が受けられるようになり、社会保険料の免除と合わせると実質的な手取り額が10割程度になる計算です。
育休中に支払いが免除されるものは何ですか?
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料といった社会保険料です。
育休期間中は、これらの社会保険料が本人負担分・会社負担分ともに全額免除されます。
将来受け取る年金額が減るなどのデメリットもありません。
ただし、住民税は前年の所得に対して課税されるため免除の対象外です。
育休2年目などに納付書が届いたら、ご自身で支払う必要があるので注意しましょう。
夫(パパ)が育休を取った場合も給料は減りますか?
はい、ママの育休と同様に、育休中は会社からの給料は支払われず、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
給付金の計算方法(休業前賃金の67%→50%)や、社会保険料が免除される仕組みも全く同じです。
夫婦で協力して育休を取得する場合も、世帯収入が一時的に減少することを前提に、家計の計画を立てておくことが大切ですね。
まとめ|育休中に貯金できない悩みは家計改善と資産運用で解消しよう
今回は、育休中に貯金ができない原因と、具体的な解決策について解説しました。
育休中に貯金ができなくなるのは、多くの家庭が経験する自然なことです。
大切なのは、現状を嘆くのではなく、固定費の見直しやスキマ時間での収入アップといった具体的な行動を起こし、将来に向けた資産形成の準備を始めることです。
育休中に貯金できない悩みの解決策まとめ
- 貯金できないのは当たり前と割り切る
- まずは家計簿アプリで収支を「見える化」
- 節約は効果の大きい「固定費」から
- スマホは格安SIM乗り換えで通信費を大幅削減
- 保険の見直しはFPへの無料相談も活用
- 育児のスキマ時間にポイ活・副業で月1万円の収入増
- 児童手当は生活費にせず将来のために別口座で貯蓄
- 社会保険料の免除など使える公的制度は漏れなく活用
- 夫婦で家計状況を共有し協力体制を築く
- 節約で浮いたお金は資産運用の原資に
育休中は、家計と向き合い、将来のお金について考える絶好の機会です。
この記事で紹介した方法で生まれた余裕資金を元手に、ぜひ「DMM FX」のようなサービスを活用して、少額からでも資産運用を始めてみてください。
今始める一歩が、あなたの未来を大きく変えるはずですよ!