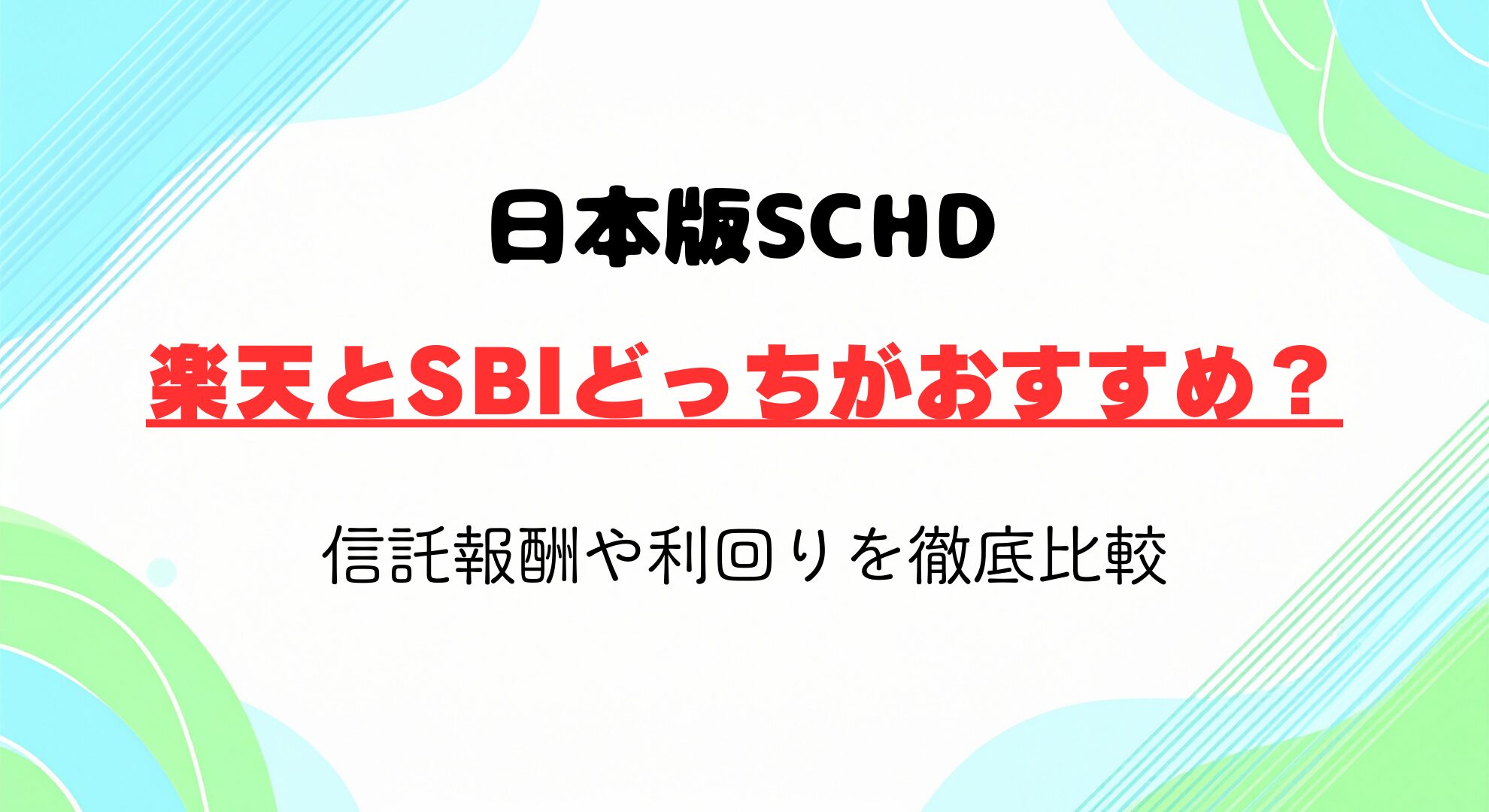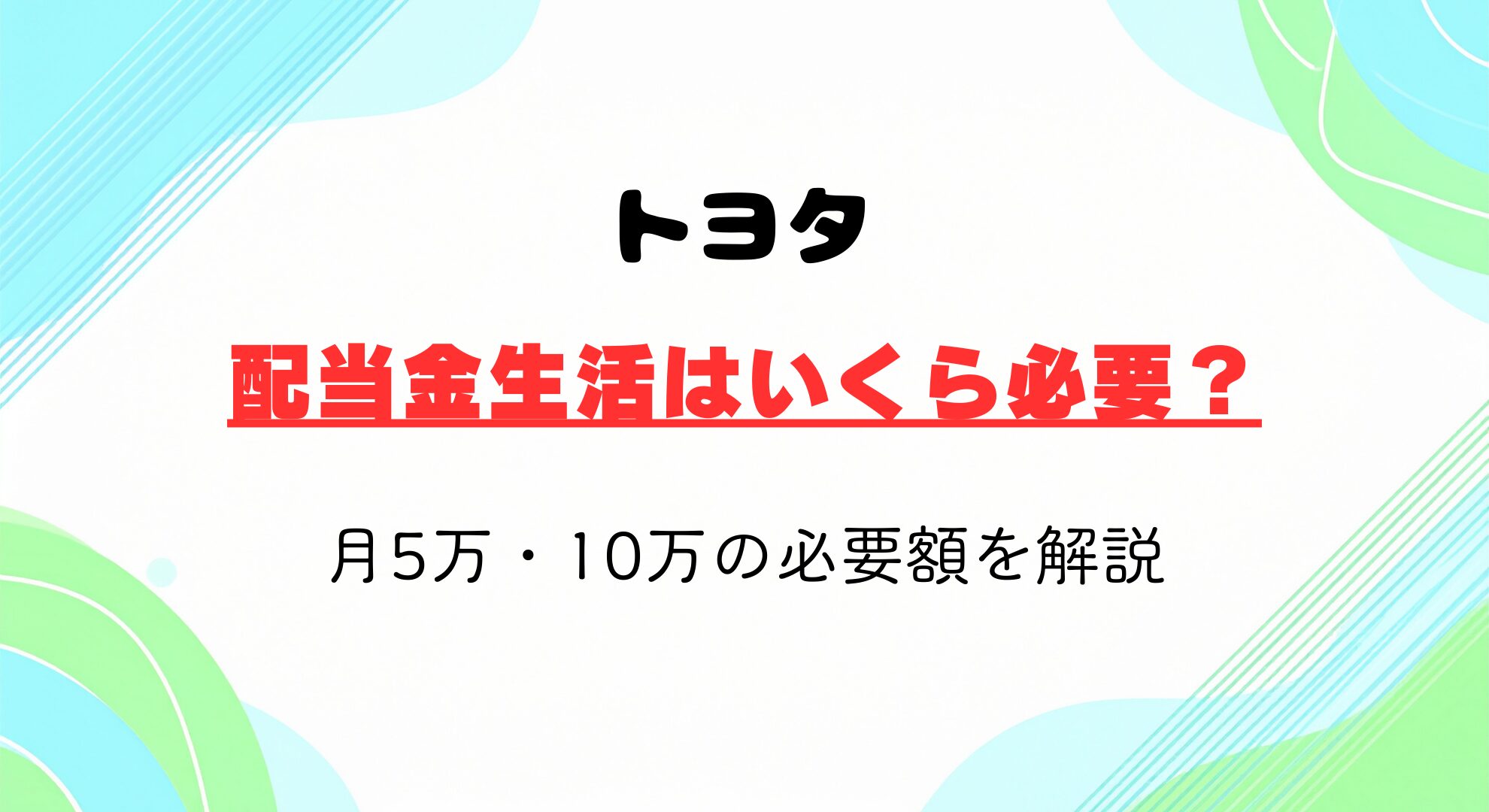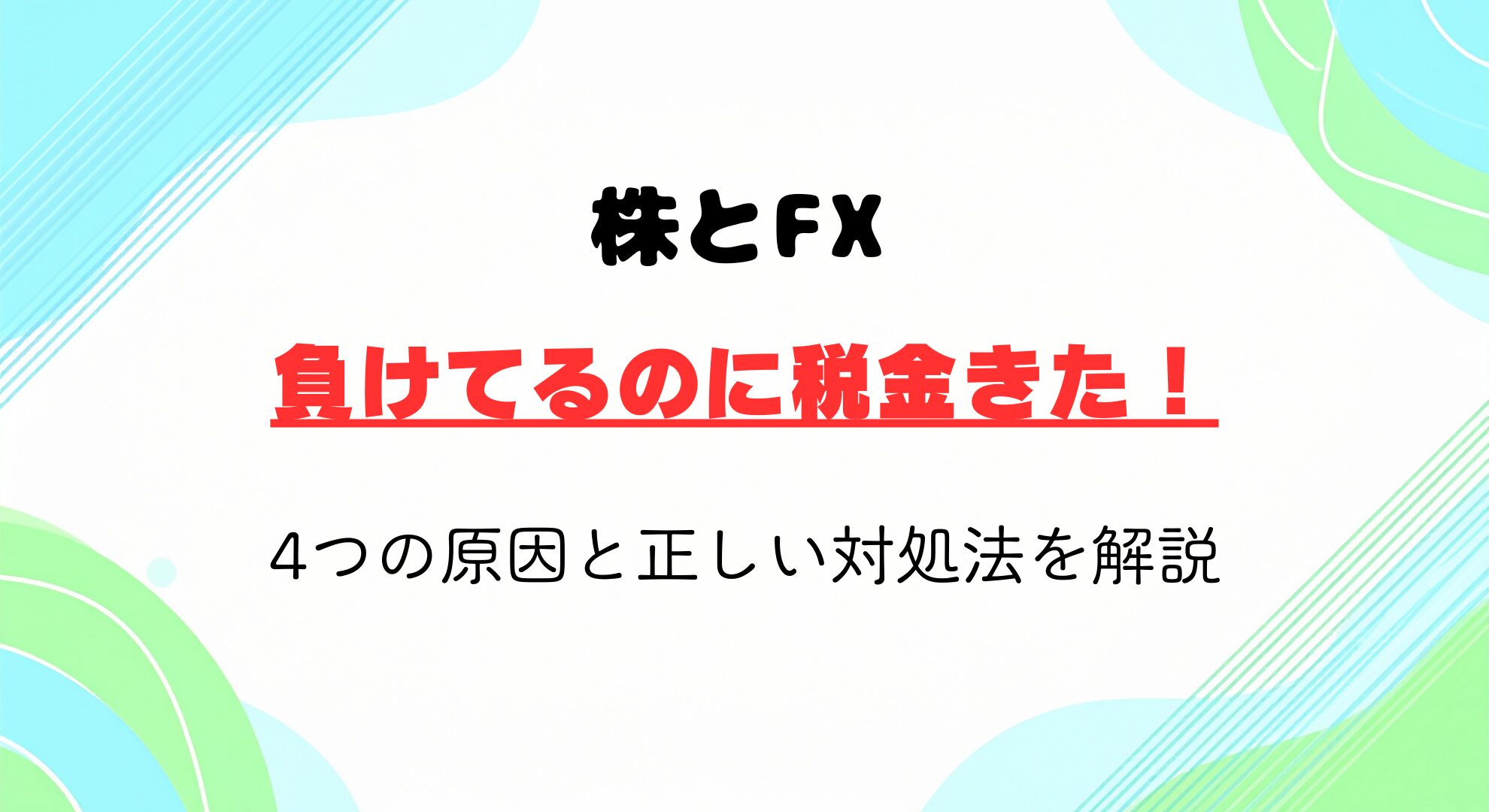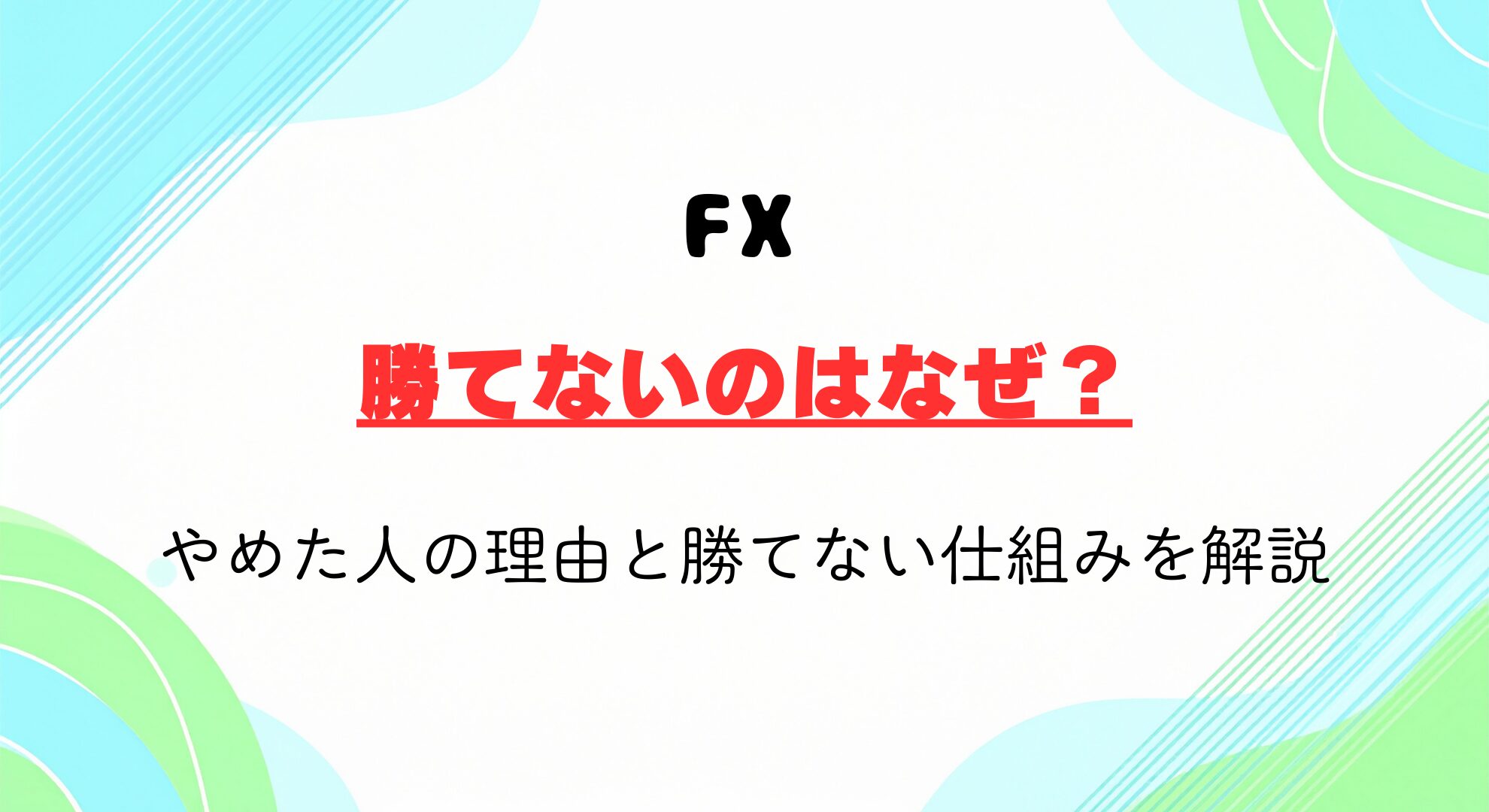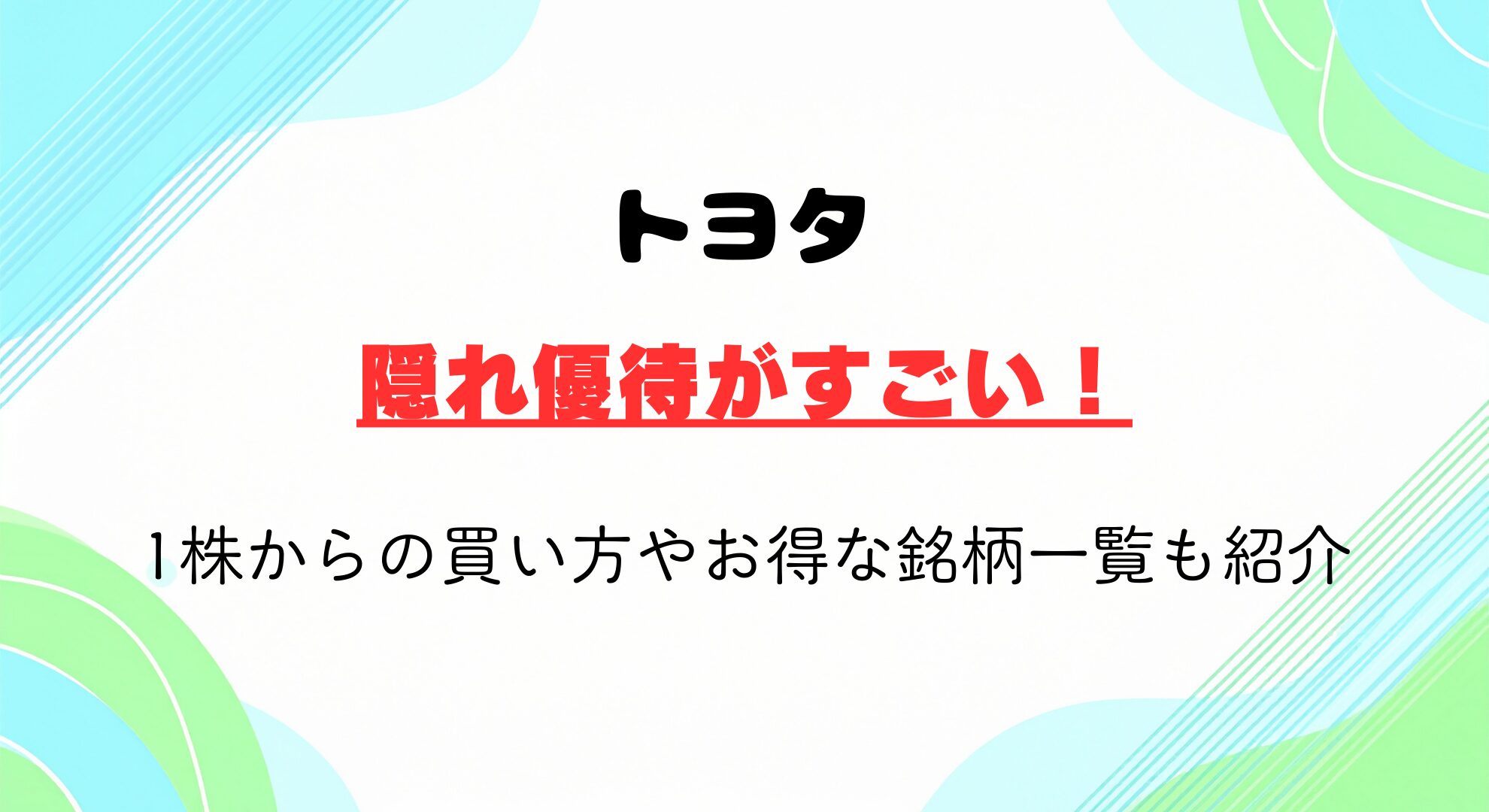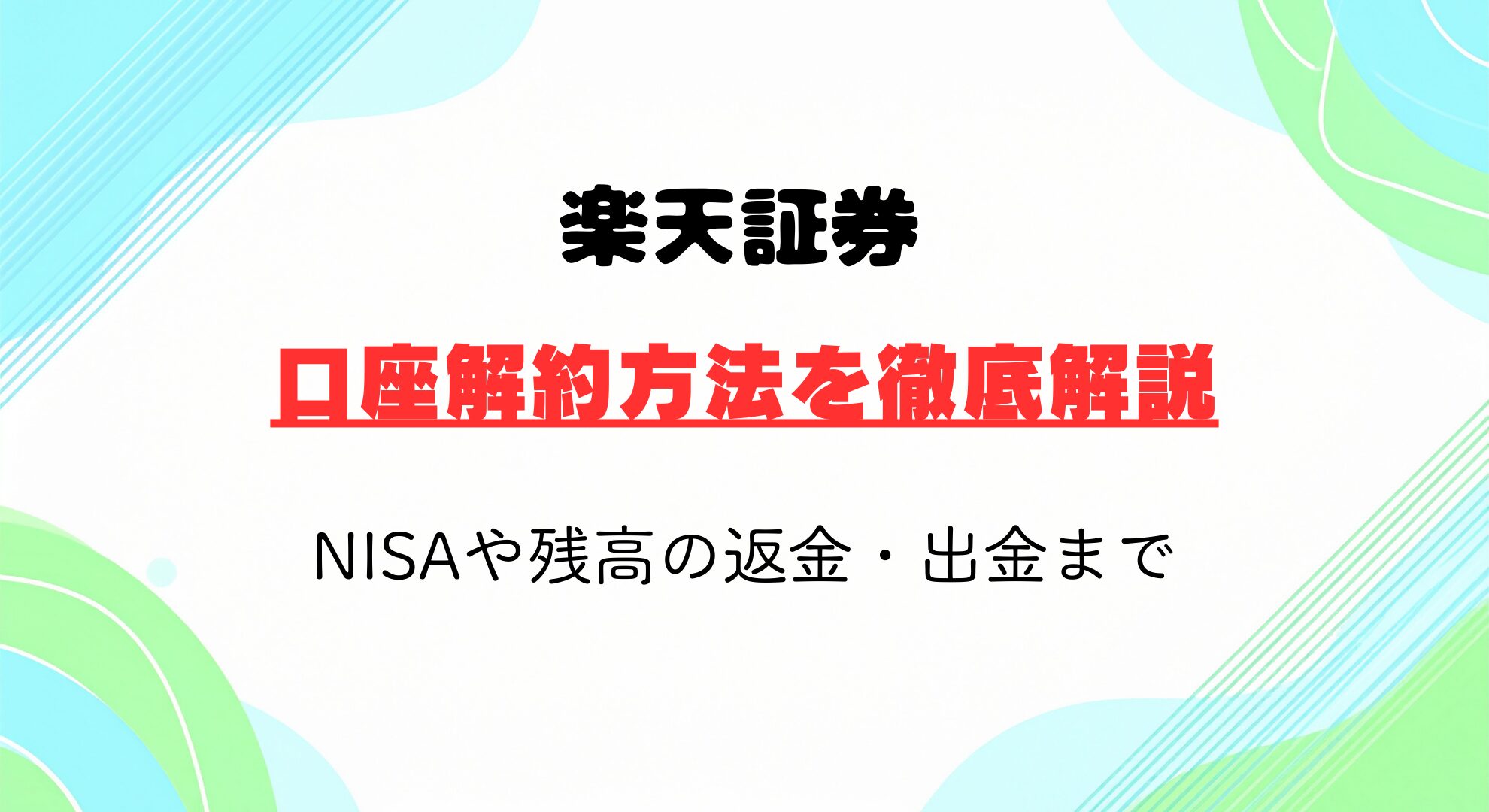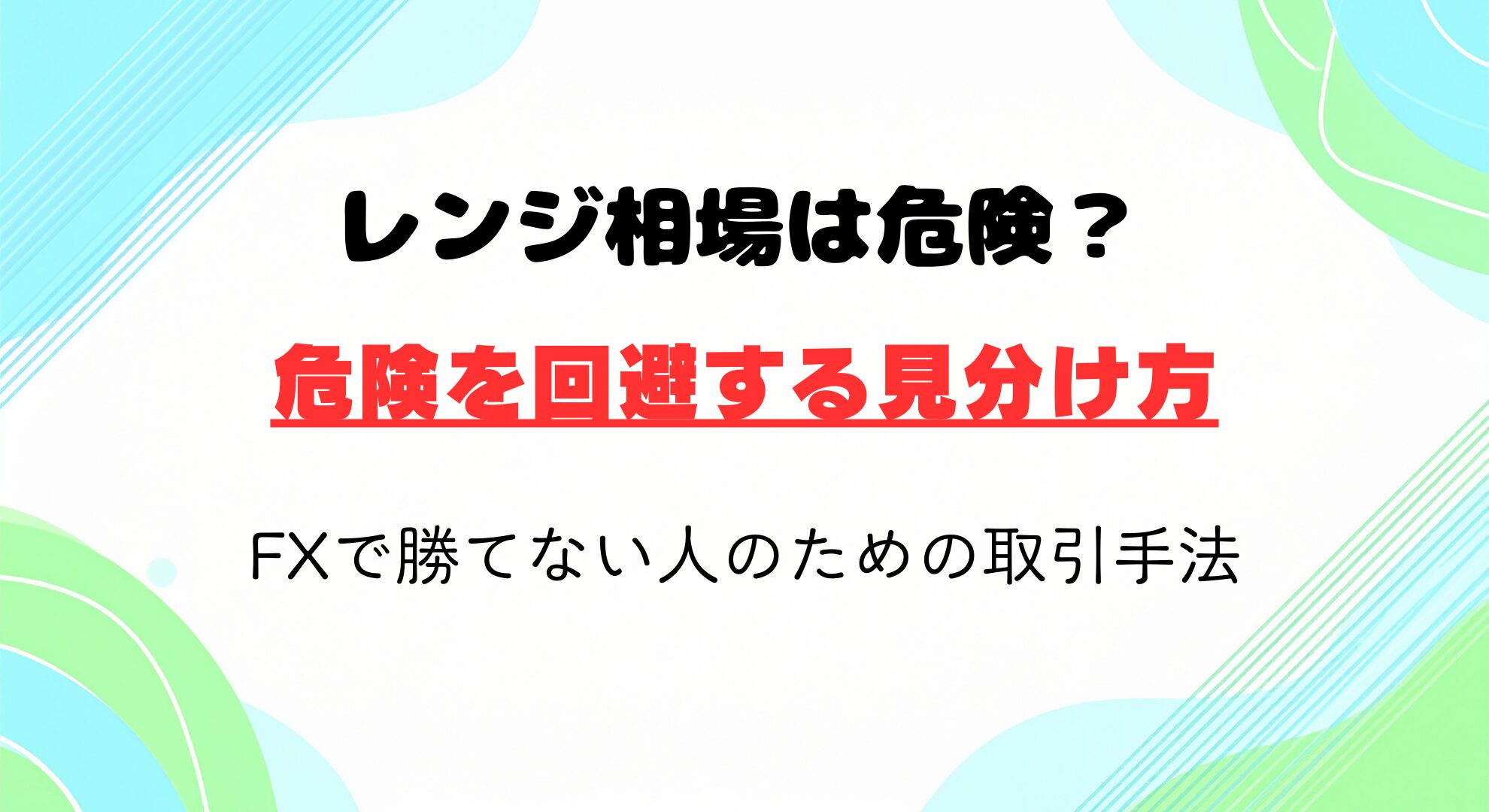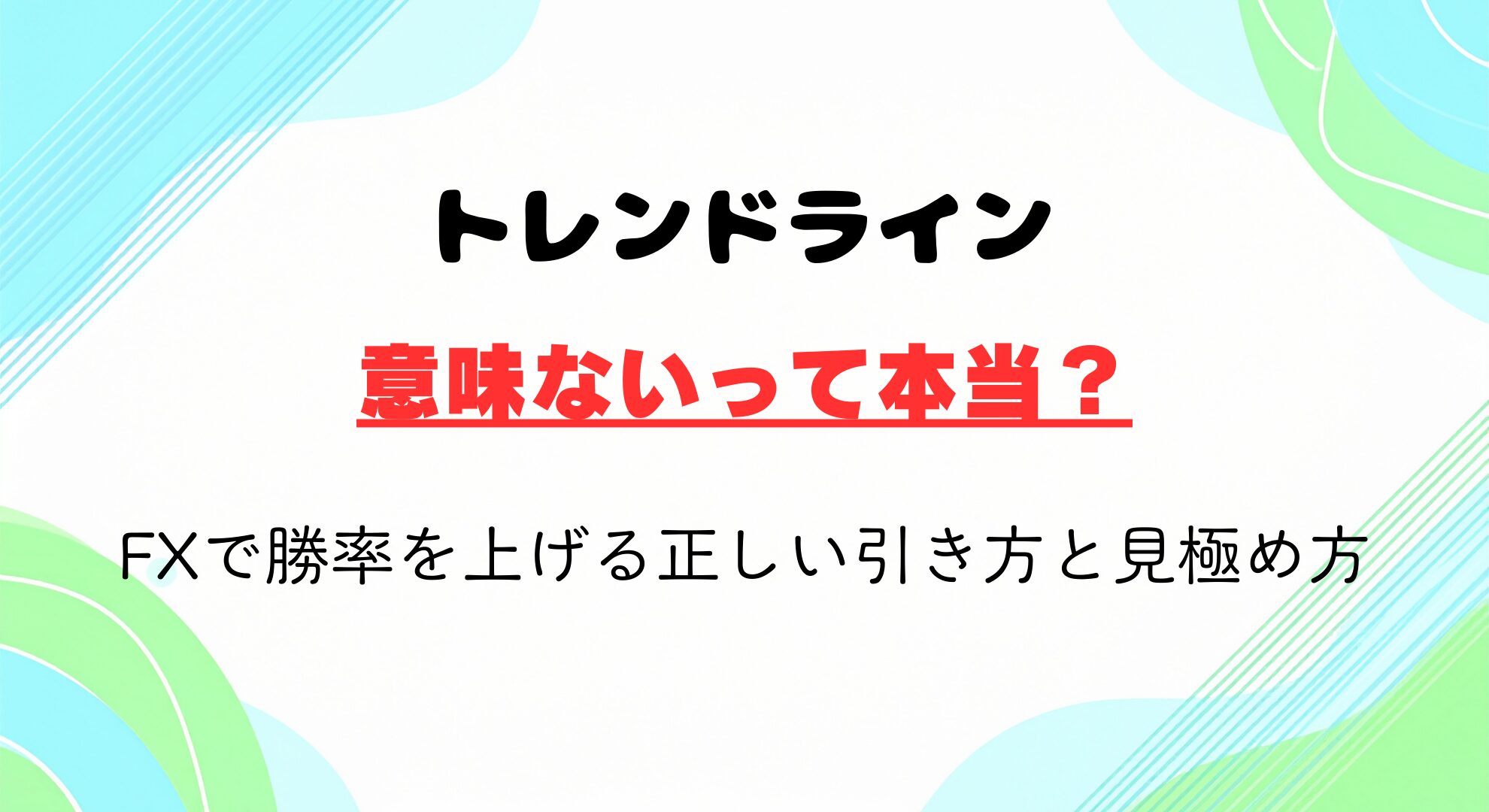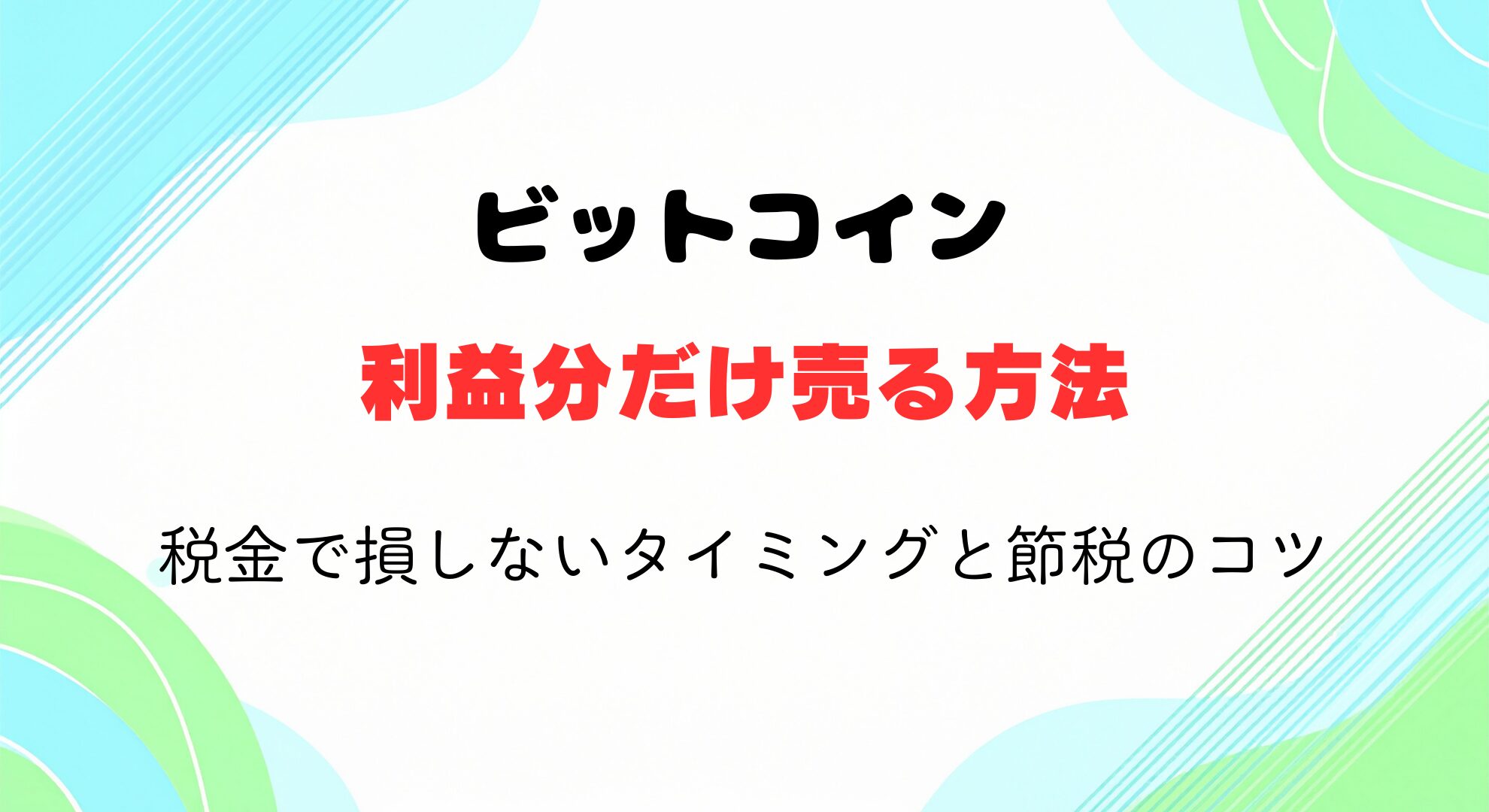この記事では、米国で人気の高配当ETF「SCHD」の日本版として注目される投資信託について、有力候補である「楽天」と「SBI」の2つのファンドを徹底比較し、どちらに投資すべきかを解説します。
日本株で安定した配当収入(インカムゲイン)を狙いたいけど、「日本版SCHD」と呼ばれるファンドが複数あって、信託報酬や構成銘柄、利回りがどう違うのか、結局どっちを選べばいいか迷っていませんか。
結論、長期的なリターンに直結するコスト(信託報酬)を最優先するなら「SBI・日本高配当株式(分配)ファンド」、本家SCHDのように財務が健全な優良企業に投資したいという安定志向なら「楽天・高配当株式・日本ファンド」がおすすめです。
SBIのファンドは年率0.099%という圧倒的な低コストが魅力で、楽天のファンドは質の高い銘柄に分散投資できる安心感があります。
どちらのファンドも新NISAの成長投資枠に対応しているため、得られた分配金を非課税にできる大きなメリットもありますね。
日本の高配当株へ手軽に投資を始めたい方は、この記事を参考にあなたの投資スタイルに合ったファンドを選んで、新NISAでの資産形成をスタートしてくださいね!
この記事でわかること
- 日本版SCHDと呼ばれる投資信託(楽天・SBI)の正体
- 楽天とSBIのファンドはどっちがおすすめか
- 信託報酬、配当利回り、構成銘柄の具体的な比較
- 高配当株投資のリスクと注意点
- 新NISA(成長投資枠)での具体的な買い方
目次
結論|日本版SCHDの本命は信託報酬0.099%のSBI!楽天は本家SCHDに近い運用に期待

「日本版SCHD」と呼ばれる高配当株ファンドを探しているなら、結論として信託報酬(コスト)の低さを最優先するならSBI、米国で人気の本家SCHDに近い思想で運用されるファンドに投資したいなら楽天が有力な選択肢です。
どちらのファンドも日本の高配当株に分散投資でき、新NISAの成長投資枠にも対応しているため、インカムゲイン(配当収入)を非課税で狙える注目の商品といえるでしょう。
ここでは、それぞれのファンドがどんな投資家に向いているのか、そして多くの投資家が意識する本家SCHDと何が違うのかを詳しく見ていきます。
日本版SCHD候補ファンドの選び方
- 信託報酬の安さで選ぶなら「SBI・日本高配当株式(分配)ファンド」
- 本家SCHDに近い指数参照で選ぶなら「楽天・高配高株式・日本ファンド」
- 【比較表】本家SCHDと日本版SCHD候補2ファンドの違いを一覧チェック
信託報酬の安さで選ぶなら「SBI・日本高配当株式(分配)ファンド」
長期的なリターンに直結するコストを何よりも重視するなら、「SBI・日本高配当株式(分配)ファンド」が一択です。
SBI・日本高配当株式(分配)ファンドの最大の魅力は、年率0.099%(税込)という驚異的な信託報酬の低さにありますね。
投資信託は保有している限りコストがかかり続けるため、信託報酬の差は長期的に見ると無視できないリターンの差となって表れます。
一般的な高配当株アクティブファンドの信託報酬が0.5%〜1.0%程度であることを考えると、SBI・日本高配当株式(分配)ファンドのコストがいかに低いかがよく分かります。
とにかく無駄なコストを徹底的に排除して、効率よく日本の高配当株に投資したいと考えている方には、SBI・日本高配当株式(分配)ファンドが最適な答えとなるでしょう。
本家SCHDに近い指数参照で選ぶなら「楽天・高配当株式・日本ファンド」
米国の本家SCHDが持つ「財務が健全で、持続的に配当を支払う優良企業を選ぶ」という投資哲学に共感するなら、「楽天・高配当株式・日本ファンド」がおすすめです。
楽天・高配当株式・日本ファンドは、ただ配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、「ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)」を参照して投資銘柄を選定します。
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)は、財務の健全性や安定した配当実績といった厳しい基準でスクリーニングを行うため、構成銘柄の質が高いのが特徴です。
一時的に利回りが高くても、業績が不安定な企業は除外されやすいため、比較的安心して長期保有しやすいといえるでしょう。
目先の利回りだけでなく、投資先の企業の質や安定性を重視する堅実な投資家の方は、楽天・高配当株式・日本ファンドを検討してみてくださいね。
【比較表】本家SCHDと日本版SCHD候補2ファンドの違いを一覧チェック
ここまで解説した楽天とSBIの2つのファンド、そして多くの投資家がベンチマークとする本家「シュワブ・米国配当株式ETF(SCHD)」の主な違いを表にまとめました。
投資対象が日本株か米国株かという大きな違いはもちろん、信託報酬や運用方針も全く異なることが分かりますね。
スクロールできます
| 比較項目 | 本家SCHD (ETF) | 楽天・高配当株式・日本ファンド | SBI・日本高配当株式(分配)ファンド |
|---|
| 投資対象 | 米国株 | 日本株 | 日本株 |
|---|
| 信託報酬/経費率 | 年率0.06% | 年率0.297% | 年率0.099% |
|---|
| 運用方針 | インデックス連動 | インデックス参照 | アクティブ |
|---|
| 為替リスク | あり | なし | なし |
|---|
| 主な販売会社 | 各証券会社 | 楽天証券 | SBI証券など |
|---|
日本版SCHDは円建てで投資できるため為替リスクがないのがメリットですが、資産が日本に集中する点も理解しておきましょう。
日本版SCHD候補「楽天」と「SBI」の配当利回り・構成銘柄を徹底比較

ここでは、日本版SCHDの有力候補である楽天とSBIの2ファンドについて、投資判断に欠かせない具体的な中身をさらに詳しく比較検討していきましょう。
利回りや構成銘柄、そして運用方針の違いを理解することで、どちらが自分の投資スタイルに合っているかが見えてくるはずです。
日本版SCHD候補ファンドの比較ポイント
- 配当利回りと分配金実績を比較|SBIがやや高利回りの傾向
- 構成銘柄を比較|SBIは独自選定、楽天はディフェンシブな大型株が中心
- 運用方針とパフォーマンスを比較|アクティブ運用のSBIとインデックス準拠の楽天
- ブログや掲示板での評判・口コミを比較|両ファンドとも資金流入は好調
配当利回りと分配金実績を比較|SBIがやや高利回りの傾向
インカムゲインを重視する上で気になる配当利回りは、直近の実績を見るとSBIのファンドがやや高い水準で推移していますね。
2025年6月時点での分配金実績から見ると、両ファンドの配当利回りはおおよそ3.5%〜4.0%程度で、日本の高配当株ファンドとして十分な水準です。
ただし、SBIのファンドはアクティブ運用ということもあり、市場環境に応じて機動的に銘柄を入れ替えることで、楽天のファンドを若干上回る利回りを実現しているようです。
分配金が受け取れる決算月は以下の通りです。
- 楽天・高配当株式・日本ファンド: 3月、6月、9月、12月
- SBI・日本高配当株式(分配)ファンド: 4月、7月、10月、1月(※初回決算以降)
どちらも年4回、四半期ごとに分配金が支払われるため、定期的なキャッシュフロー作りに貢献してくれるでしょう。
構成銘柄を比較|SBIは独自選定、楽天はディフェンシブな大型株が中心
両ファンドのパフォーマンスを将来的に左右する最も大きな違いは、投資する銘柄の選び方、つまりポートフォリオの中身にあります。
楽天・高配当株式・日本ファンドは、先述の通り「ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス」を参照するため、構成銘柄はKDDI、NTT、JT(日本たばこ産業)といった、誰でも知っているようなディフェンシブな大型株が中心です。
一方で、SBI・日本高配当株式(分配)ファンドは特定の指数に連動しないアクティブファンドなので、ファンドマネージャーが独自の基準で投資銘柄を選定します。
| 比較項目 | 楽天・高配当株式・日本ファンド | SBI・日本高配当株式(分配)ファンド |
|---|
| 銘柄選定の基準 | ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックスを参照 | 独自のファンダメンタル評価・分析 |
|---|
| ポートフォリオの特徴 | 大型のディフェンシブ銘柄が中心 | 市場平均比で高配当な銘柄に集中投資 |
|---|
| 代表的な構成銘柄 | KDDI, NTT, SOMPOホールディングス, 日本たばこ産業(JT)など | 非公開(定期的に見直し) |
|---|
安定感のあるポートフォリオを好むなら楽天、プロの銘柄選定力に期待したいならSBI、という選び方もできますね。
運用方針とパフォーマンスを比較|アクティブ運用のSBIとインデックス準拠の楽天
運用方針の違いは、設定されてからのパフォーマンスにもしっかり表れています。
SBI・日本高配高株式(分配)ファンドはアクティブ運用のため、市場環境が良い局面ではベンチマークを上回るリターンを積極的に狙いにいきますが、逆に市場が下落する局面ではインデックス以上に下げる可能性も秘めています。
対して、楽天・高配当株式・日本ファンドは指数を参照するため、良くも悪くも市場平均から大きく乖離することなく、比較的安定した値動きが期待できるでしょう。
どちらが良いというわけではなく、自分のリスク許容度に合わせて選ぶことが大切です。
積極的にリターンを狙いたいならSBI、安定感を重視するなら楽天が向いているといえます。
ブログや掲示板での評判・口コミを比較|両ファンドとも資金流入は好調
ブログやSNS、掲示板での評判を見ると、どちらのファンドも新NISAの成長投資枠の有力な投資先として非常に注目度が高く、順調に純資産を増やしています。
SBI・日本高配当株式(分配)ファンドについては、やはり「信託報酬0.099%は革命的」といったコストの低さを評価する声が圧倒的に多いですね。
楽天・高配当株式・日本ファンドに対しては、「本家SCHDの日本版というコンセプトが分かりやすい」「構成銘柄が王道で安心できる」といった、安定性や信頼性を評価する口コミが目立ちます。
多くの個人投資家から支持されていることは、これから投資を始める上で一つの安心材料になるでしょう。
【要注意】日本版SCHDに投資する前に知るべき高配当株投資のリスク

高配当株投資は定期的な分配金が魅力ですが、もちろんメリットばかりではありません。
思わぬ落とし穴にはまらないよう、投資を始める前に必ず知っておくべきリスクや注意点をしっかり確認しておきましょう。
高配当株投資の主なリスク
- タコ足分配の懸念は基準価額の推移を必ずチェックして回避
- 値上がり益が限定的になる可能性も考慮し成長株ファンドと併用
- 為替変動を受けないメリットと日本経済に依存するリスクを理解する
タコ足分配の懸念は基準価額の推移を必ずチェックして回避
高配当ファンドで最も警戒すべきなのが、投資した元本を切り崩して分配金を支払う、いわゆる「タコ足分配」です。
タコ足分配が行われると、見かけ上の分配金は高くても、ファンドの基準価額は下落し続けるため、実質的に自分の資産が目減りしている状態になります。
タコ足分配に陥っているファンドを見抜くには、分配金の利回りだけでなく、必ずファンドの基準価額が右肩下がりになっていないかセットで確認することが重要です。
新しいファンドはまだ実績が少ないですが、投資信託の月次レポートなどで定期的に基準価額の推移をチェックする習慣をつけましょう。
値上がり益が限定的になる可能性も考慮し成長株ファンドと併用
高配当株は、すでに事業が成熟して安定期に入った大企業が多いため、S&P500のような市場全体に連動するインデックスファンドと比べて、株価自体の値上がり益(キャピタルゲイン)が伸び悩む可能性があります。
インカムゲイン(分配金)だけでなく、資産全体の成長スピードも重視するなら、ポートフォリオの一部に全世界株式や米国株式などの成長株ファンドを組み合わせるのがおすすめです。
例えば、「守りの高配当株ファンド」と「攻めの成長株ファンド」を組み合わせることで、よりバランスの取れた資産形成を目指せますね。
為替変動を受けないメリットと日本経済に依存するリスクを理解する
日本版SCHDは円建てで投資するため、米国株投資で常に意識する為替変動のリスクを直接受けない点が大きなメリットですね。
一方で、自分の資産が「日本円」と「日本経済」に集中してしまうリスクも忘れてはいけません。
将来の円安に備えたり、ポートフォリオのリスクを多様化させたりする一つの考え方として、為替の変動そのものを収益機会に変えるFXのような金融商品もあります。
例えば、総合力が高く初心者にも使いやすいと評判のDMM FXなら、スマホアプリで手軽に為替の動きを意識した取引を始めることも可能です。
新NISAで日本版SCHDを買う方法|楽天証券・SBI証券での手順を解説

投資したいファンドの魅力とリスクを理解したら、次はいよいよ購入です。
ここでは、税金のメリットを最大限に活かせる新NISAを使った具体的な買い方を、主要なネット証券である楽天証券とSBI証券を例に解説します。
日本版SCHDの買い方
- 新NISAの成長投資枠を活用して分配金を非課税で受け取る
- SBI証券で「SBI・日本高配当株式」を買う具体的な手順
- 楽天証券で「楽天・高配当株式・日本ファンド」を買う具体的な手順
新NISAの成長投資枠を活用して分配金を非課税で受け取る
今回紹介した「楽天・高配当株式・日本ファンド」と「SBI・日本高配当株式」は、どちらも新NISAの「成長投資枠」の対象銘柄です。
通常、投資信託の分配金には約20%の税金がかかりますが、新NISAの口座内で得た分配金は全額非課税で受け取れます。
年間240万円という大きな非課税投資枠を有効に活用して、効率的にインカムゲインを増やしていきましょう。
NISA口座での分配金は、再投資に回しても非課税枠を消費しません。
SBI証券で「SBI・日本高配当株式」を買う具体的な手順

信託報酬の低さが魅力の「SBI・日本高配当株式」は、その名の通りSBI証券で購入するのが基本となります。
SBI証券の口座にログイン後、トップページの検索窓に「SBI・日本高配当株式」と入力して検索してください。
ファンドの詳細ページが表示されたら、「金額買付」または「積立買付」を選択し、購入金額や積立設定を入力すれば手続きは完了です。
NISA口座で購入する場合は、取引の選択画面で「NISA(成長投資枠)」を選ぶのを忘れないようにしましょう。
コストを最重視するなら、SBI証券で口座開設して始めるのがおすすめです。
楽天証券で「楽天・高配当株式・日本ファンド」を買う具体的な手順

「楽天・高配当株式・日本ファンド」に投資するなら、楽天証券で購入するのがスムーズです。
こちらもSBI証券と同様に、楽天証券にログイン後、ファンド名を検索して購入手続きを進めます。
楽天証券なら、投資信託の購入に楽天ポイントが利用できたり、保有残高に応じてポイントが貯まったりするメリットもありますね。
楽天のサービスを普段からよく利用する方や、指数の信頼性を重視する方は楽天証券を選びましょう。
日本版SCHDに関してよくある質問
最後に日本版SCHDに関してよくある質問に回答します。
よくある質問
- 結局、「日本版SCHD」は楽天とSBIのどっちがおすすめですか?
- 日本版SCHD(楽天・SBI)の分配金はいつもらえますか?
- 日本版SCHDは最低いくらから投資できますか?
- 日本版SCHDは新NISAの「つみたて投資枠」で買えますか?
- 高配当株投資にはどんなデメリットやリスクがありますか?
- 年間12万円(月1万円)の分配金をもらうには、いくら投資が必要ですか?
- SBIの日本高配当株式ファンドは楽天証券でも買えますか?
結局、「日本版SCHD」は楽天とSBIのどっちがおすすめですか?
投資方針によっておすすめは異なりますが、コストを最優先するなら「SBI・日本高配当株式」、本家SCHDに近い思想や安心感を重視するなら「楽天・高配高株式・日本ファンド」がおすすめです。
SBIのファンドは信託報酬が年率0.099%と圧倒的に低く、楽天のファンドは財務健全性などで厳選された指数を参照しているという特徴があります。
日本版SCHD(楽天・SBI)の分配金はいつもらえますか?
どちらのファンドも年4回、3ヶ月ごとに分配金が支払われます。
決算月はそれぞれ異なり、楽天のファンドは3月・6月・9月・12月、SBIのファンドは1月・4月・7月・10月となっています。
日本版SCHDは最低いくらから投資できますか?
楽天証券やSBI証券といった主要なネット証券では、どちらのファンドも100円から投資を始めることができます。
少額からコツコツ積立投資をしたい方でも、気軽にスタートできるのが魅力ですね。
日本版SCHDは新NISAの「つみたて投資枠」で買えますか?
いいえ、この記事で紹介している楽天とSBIのファンドは、どちらも新NISAの「つみたて投資枠」では購入できません。
金融庁が定める「つみたて投資枠」の対象となるための要件を満たしていないため、「成長投資枠」(年間240万円)を利用して購入することになります。
高配当株投資にはどんなデメリットやリスクがありますか?
主なリスクとして、投資元本を取り崩して分配金を支払う「タコ足分配」の可能性や、株価の値上がり益がインデックスファンドなどと比べて限定的になる可能性がある点が挙げられます。
分配金だけでなく、ファンドの基準価額がしっかり成長しているかも合わせて確認することが大切です。
年間12万円(月1万円)の分配金をもらうには、いくら投資が必要ですか?
仮に配当利回りを年率3.5%と仮定すると、税金を考慮しない場合、年間12万円の分配金を得るためには約343万円の投資資金が必要です。
ただし、配当利回りは常に変動しますし、NISA口座以外では分配金に約20%の税金がかかるため、あくまで目安として考えておきましょう。
SBIの日本高配当株式ファンドは楽天証券でも買えますか?
はい、「SBI・日本高配当株式(分配)ファンド」は楽天証券でも購入可能です。
ただし、SBI証券で保有すると投信保有ポイントが付与されるなどのメリットがあるため、特別な理由がなければSBI証券で購入するのがおすすめです。
まとめ|日本版SCHDは信託報酬最安のSBIか、本家思想の楽天かで見極めよう!
今回は、日本版SCHDの有力候補である楽天とSBIの2つの高配当株ファンドについて、その違いや選び方を解説しました。
どちらのファンドも日本の高配当株に手軽に分散投資でき、新NISAで非課税の恩恵も受けられる優れた選択肢です。
最終的にどちらを選ぶかは、あなたが何を重視するかによって決まります。
| 比較項目 | 楽天・高配当株式・日本ファンド | SBI・日本高配当株式(分配)ファンド |
|---|
| 選ぶ決め手 | 指数の信頼性・安心感 | 圧倒的な低コスト |
|---|
| 信託報酬(税込) | 年率0.297% | 年率0.099% |
|---|
| 運用方針 | インデックス参照 | アクティブ |
|---|
| 主な販売会社 | 楽天証券 | SBI証券 |
|---|
日本版SCHDまとめ
- 日本版SCHDの有力候補は「楽天」と「SBI」の2ファンド
- コスト最優先なら信託報酬0.099%の「SBI・日本高配当株式」
- 本家SCHDに近い運用思想なら「楽天・高配当株式・日本ファンド」
- どちらも新NISAの成長投資枠で購入可能
- 配当利回りの目安は3.5%〜4.0%程度
- 分配金はどちらも年4回(四半期ごと)
- SBIは独自選定、楽天は大型株中心の安定ポートフォリオ
- タコ足分配や値上がり益が鈍化するリスクも理解が必要
- 為替リスクはないが、資産が日本に集中する点は注意
- 楽天証券やSBI証券なら100円から手軽に始められる
高配当株投資は、将来のキャッシュフローを増やすための有効な手段の一つです。
この記事で解説した比較ポイントや注意点を参考に、ご自身の投資スタイルに合ったファンドを選んで、将来のための資産運用を始めてみましょう。