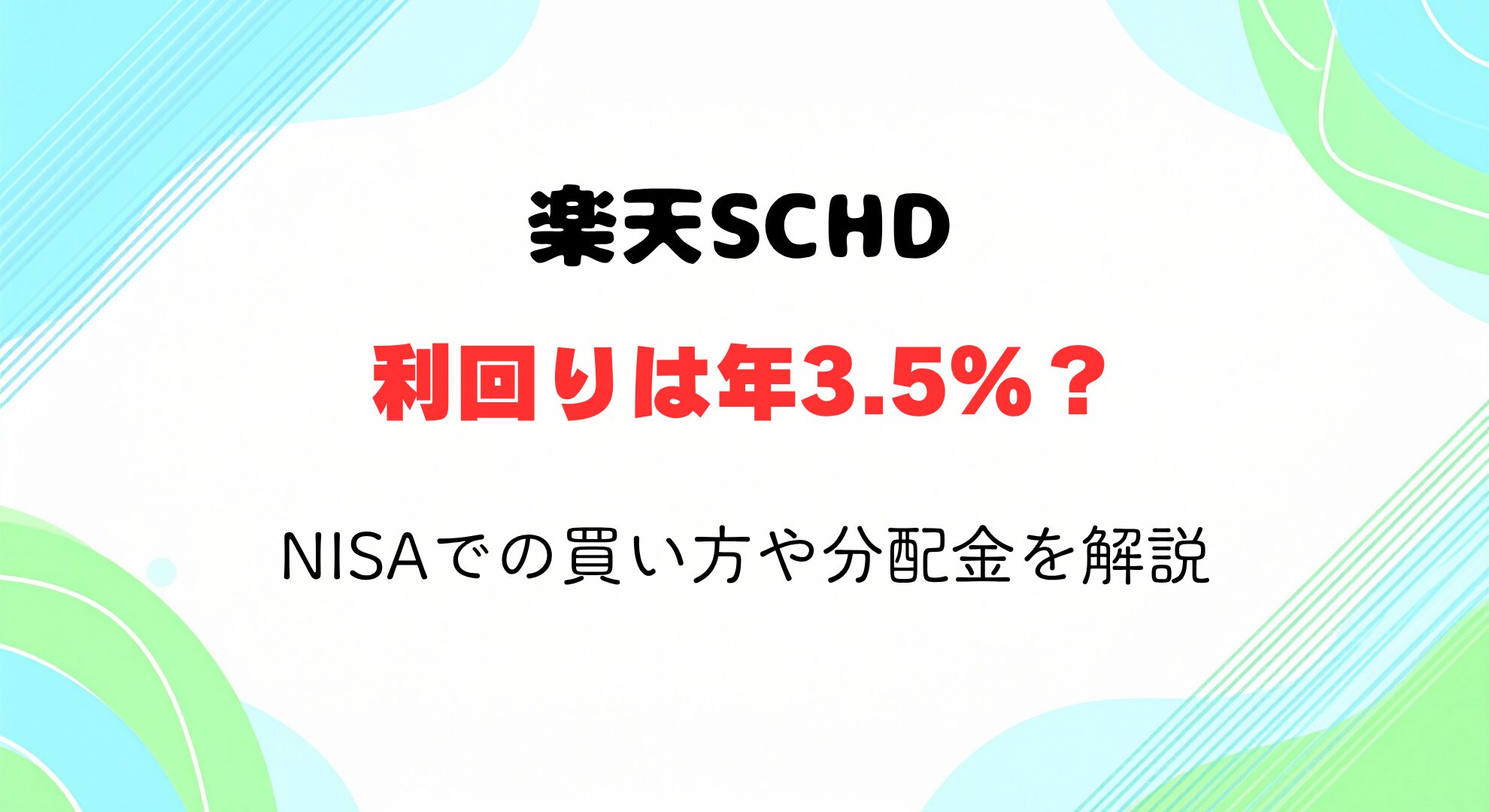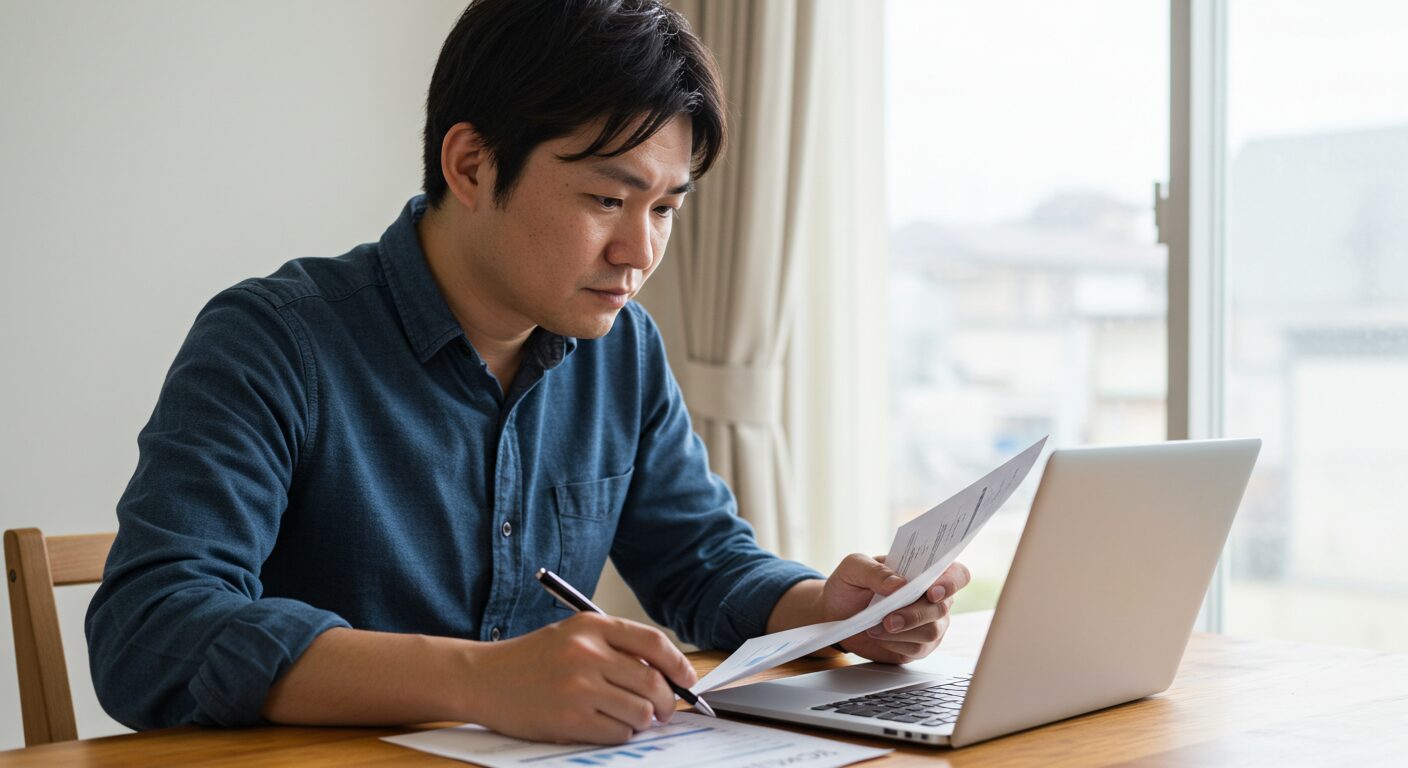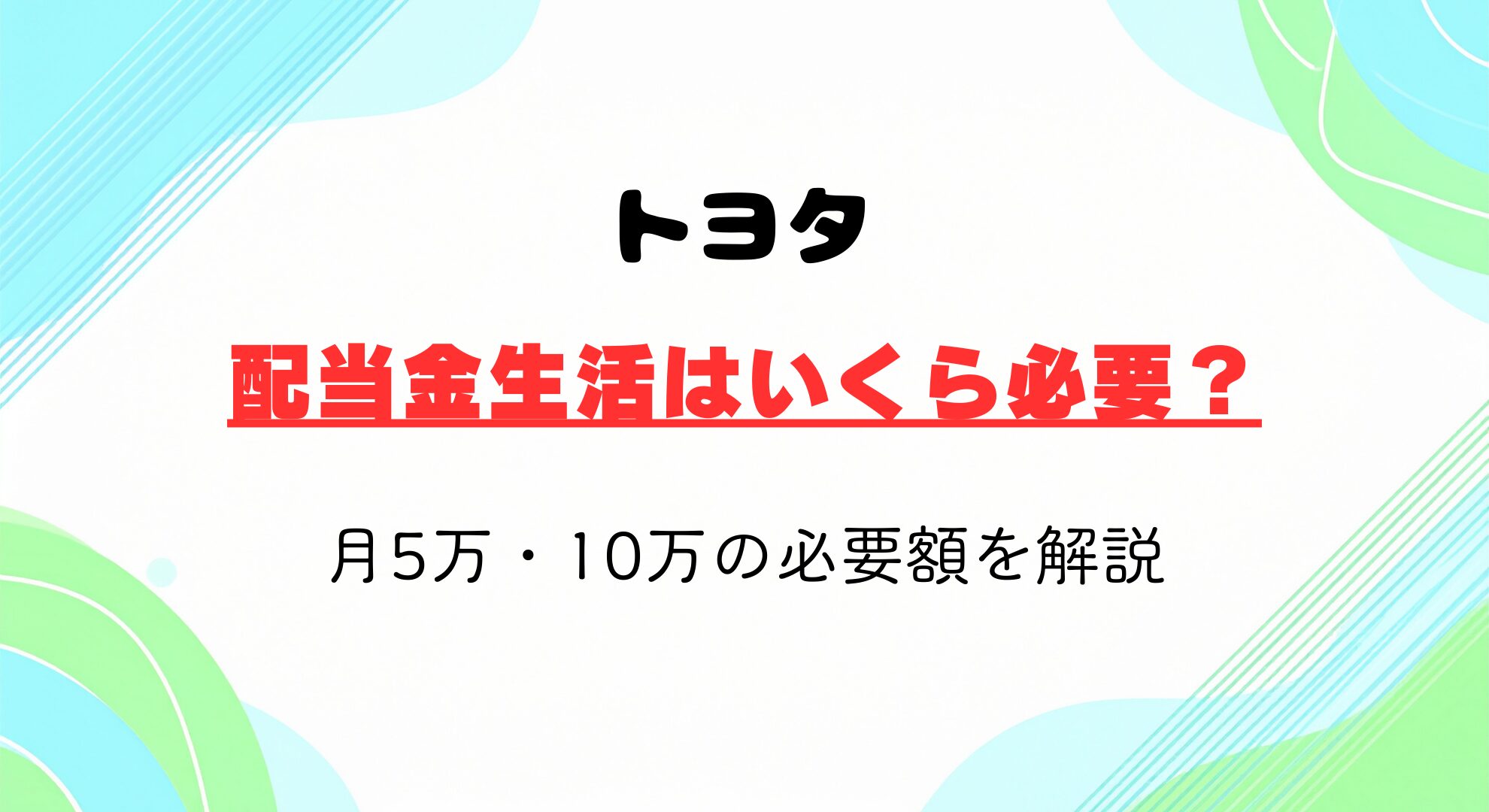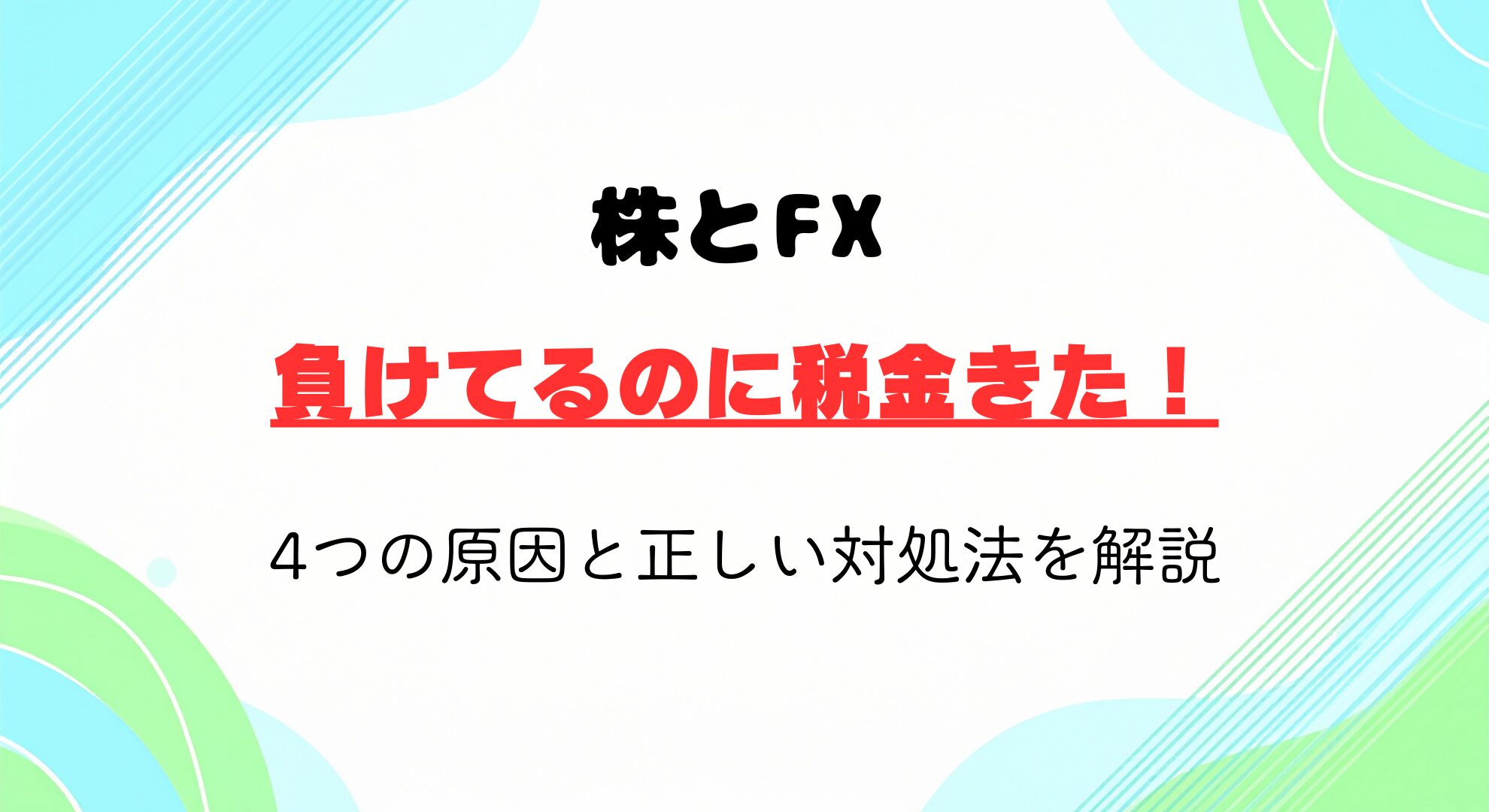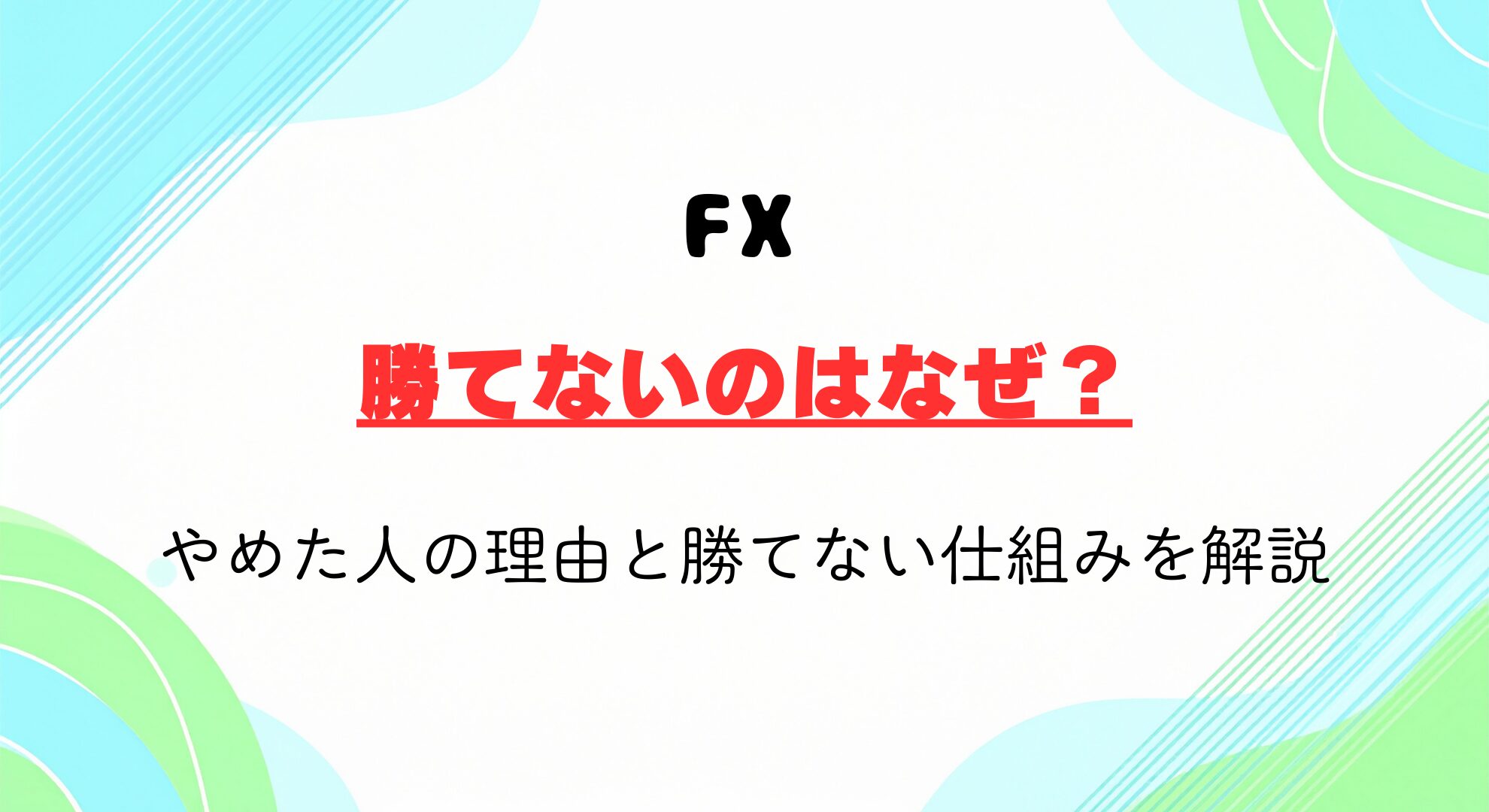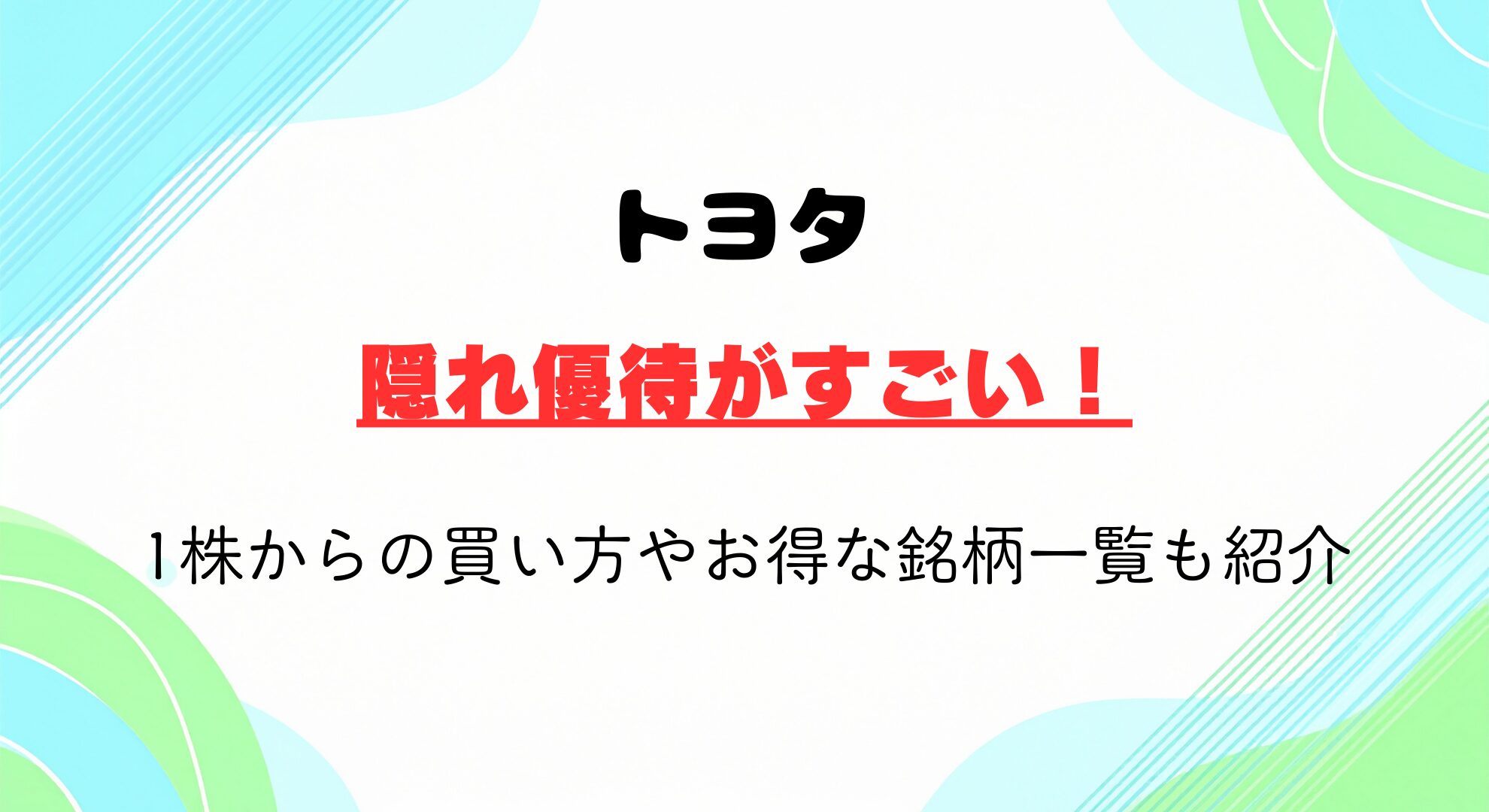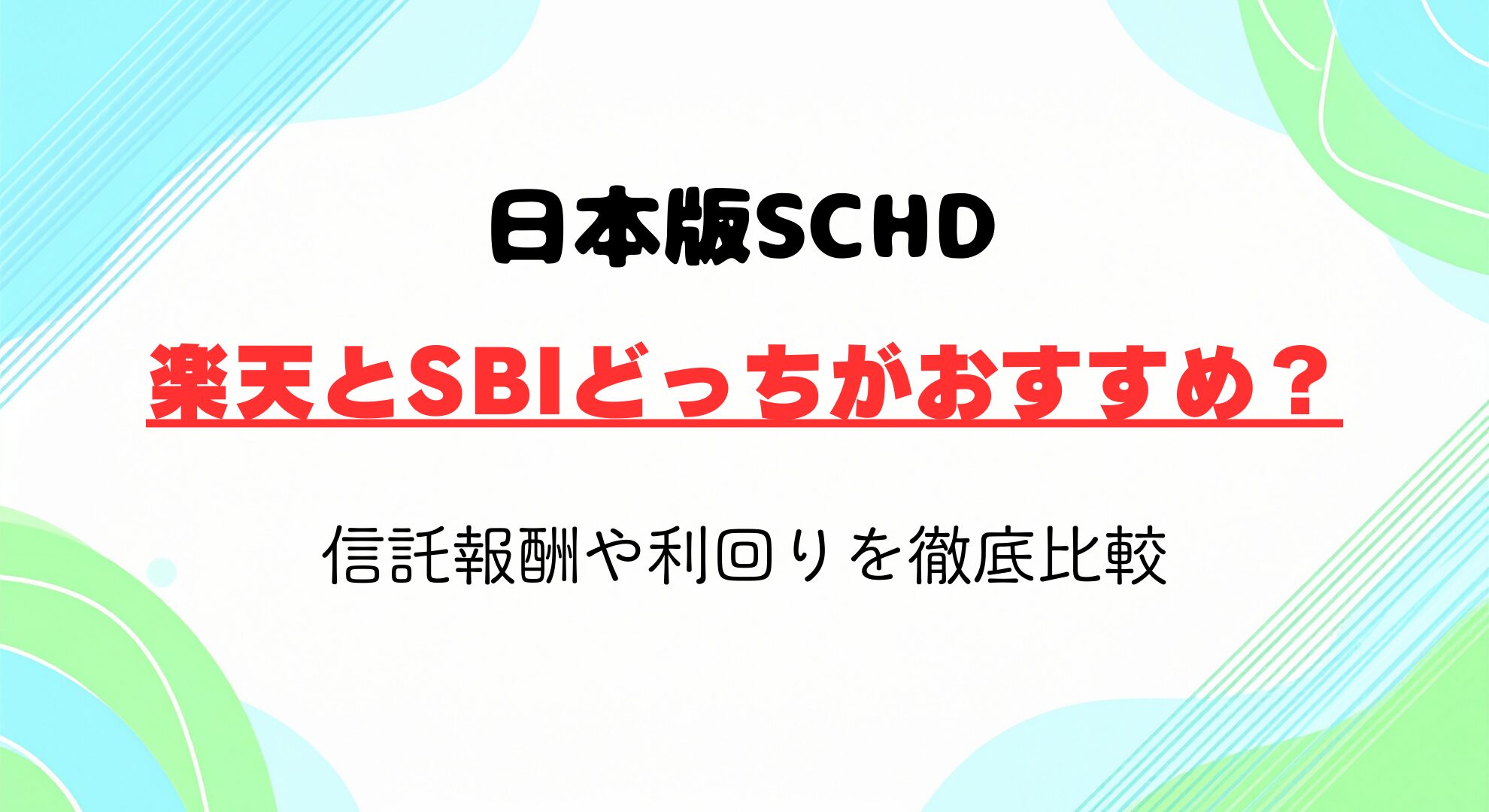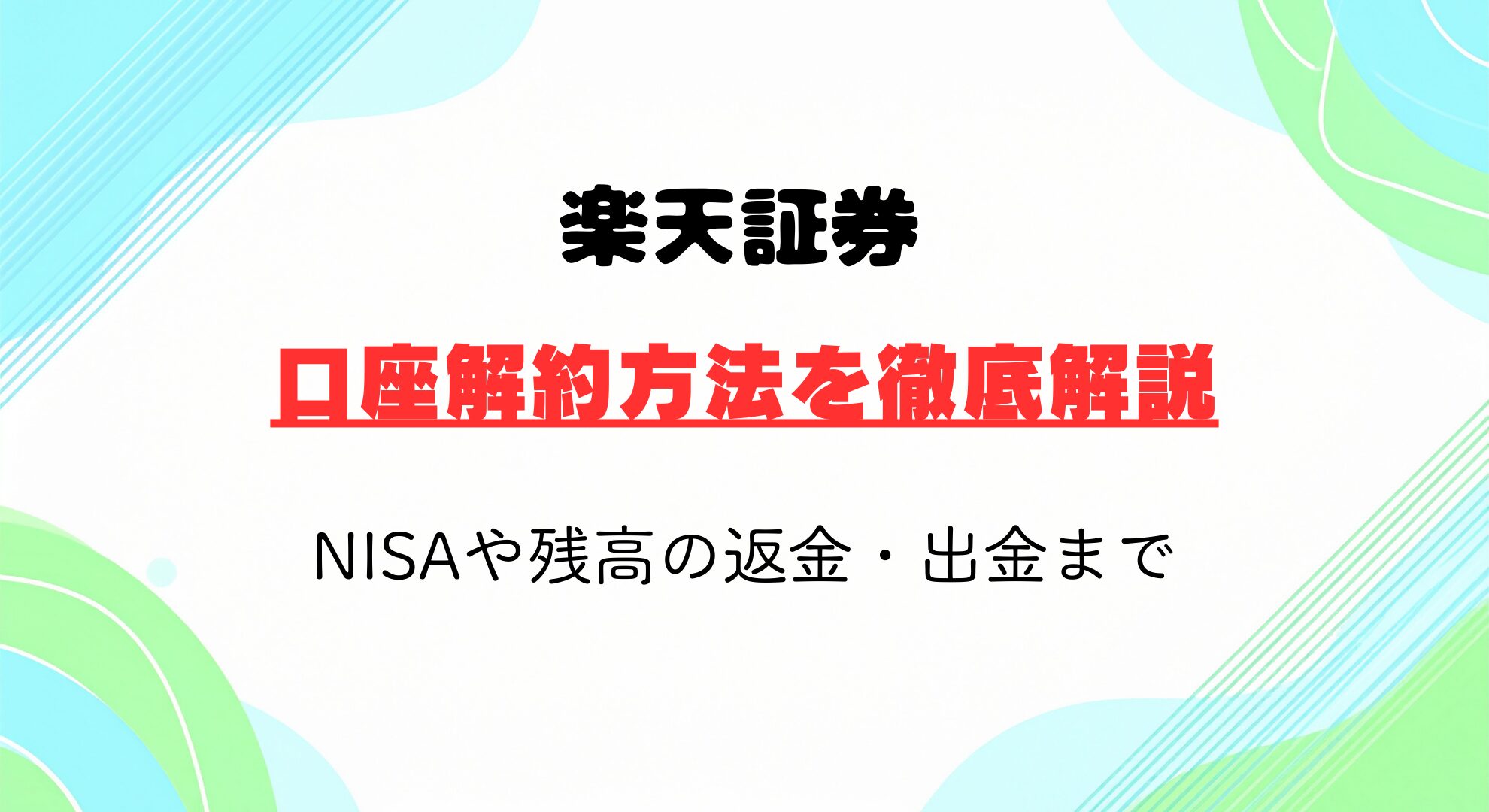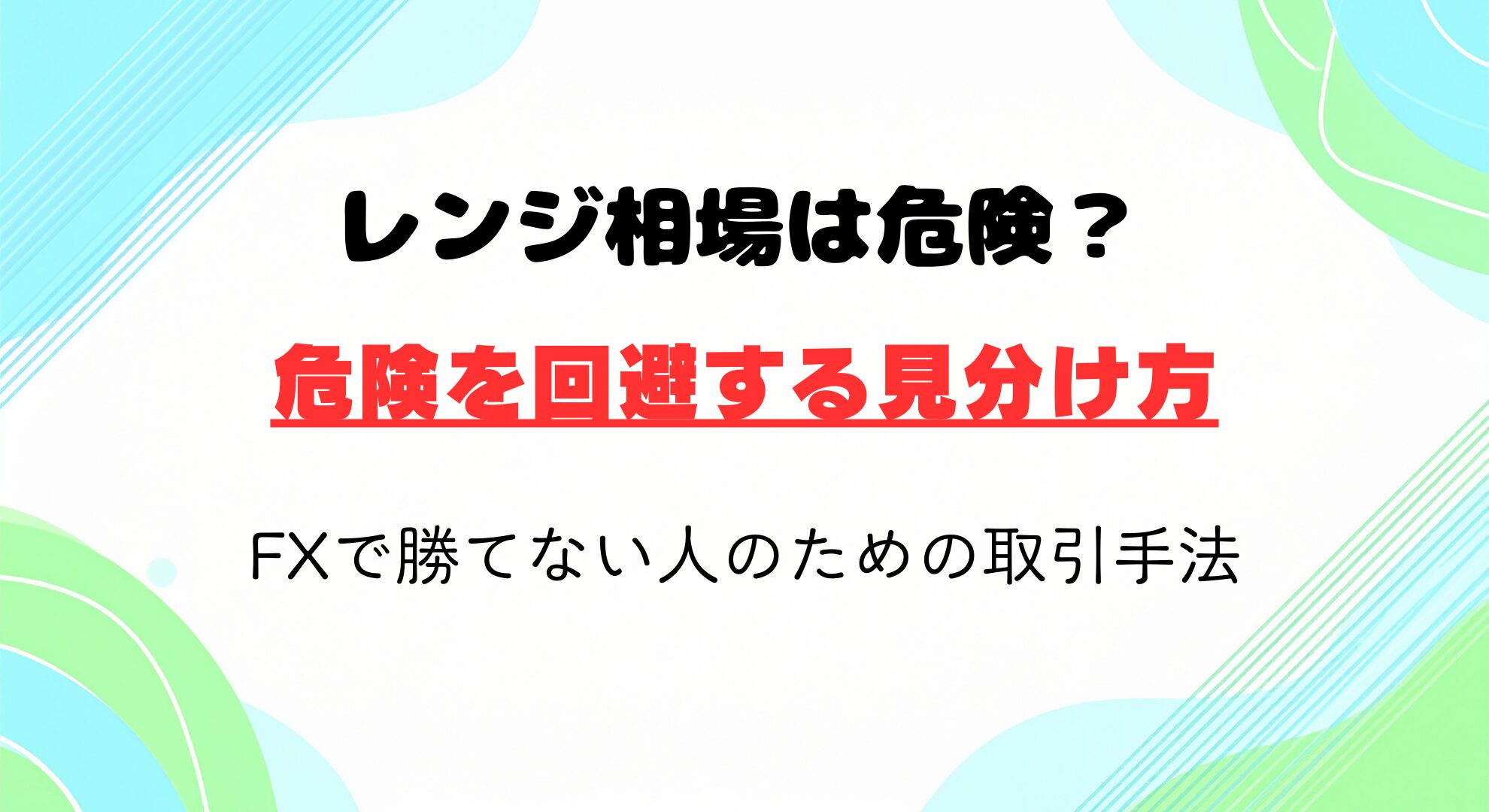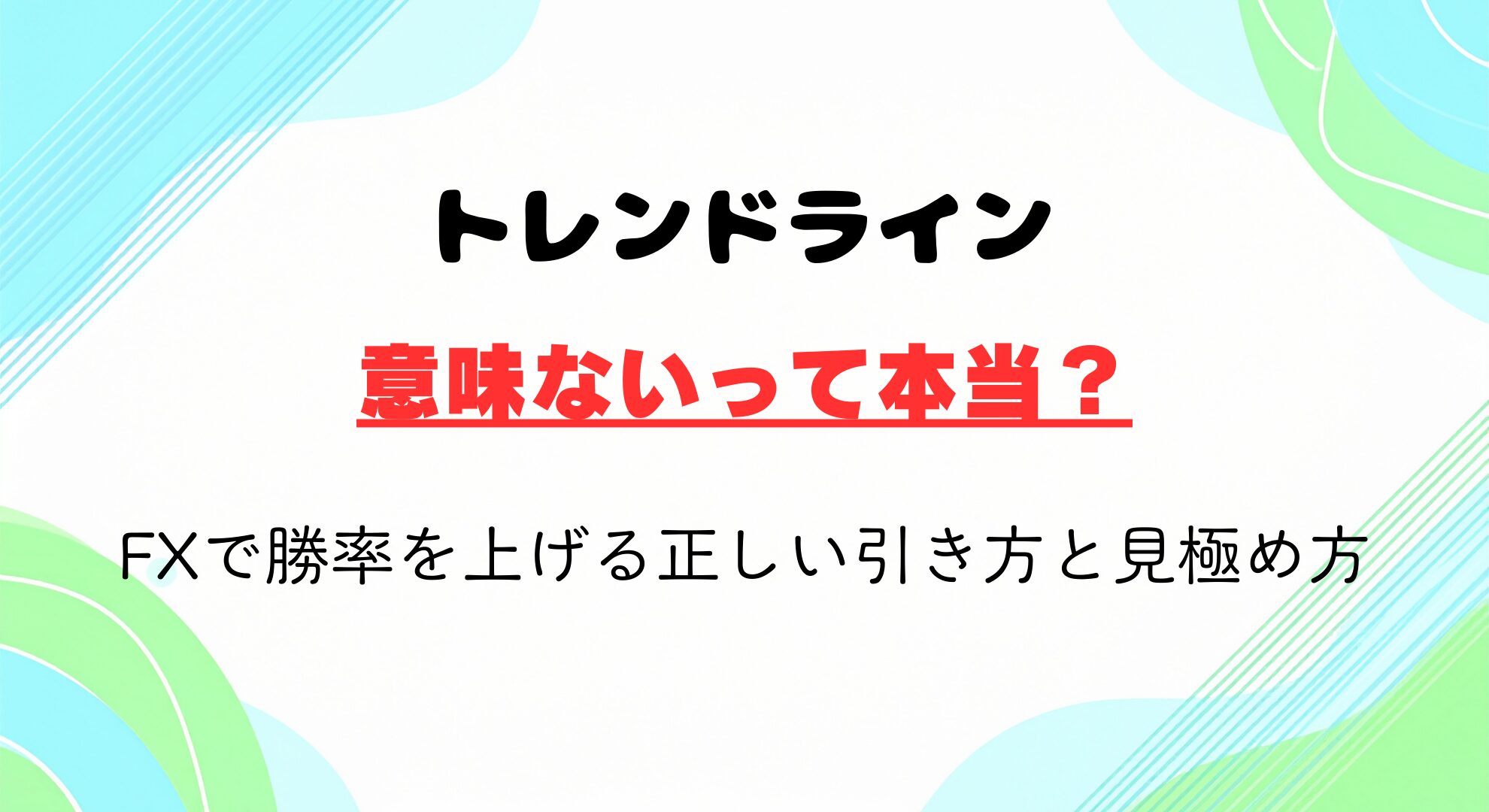この記事では、人気の高配当ファンド「楽天SCHD」の利回りについて、具体的なシミュレーションから注意点、お得な買い方まで徹底解説します。
「将来のために配当金生活を目指したいけど、どの商品に投資すればいいか分からない」「楽天SCHDが人気みたいだけど、実際の利回りはどれくらいで、本当に安心して投資できるの?」と悩んでいませんか?
結論、楽天SCHDは年3.5%前後の安定した分配金利回りが期待でき、新NISAの非課税メリットを活かして「じぶん年金」を作るのに最適な投資信託です。
楽天SCHDは、財務が健全な米国の優良企業約100社に厳選投資しており、過去の実績からも高い増配率が魅力です。
楽天証券で100円から積立が可能で、3ヶ月に一度の分配金は、投資を続ける上での大きなモチベーションになるでしょう。
この記事を参考に、あなたも楽天SCHDで将来に向けた資産形成の第一歩を踏み出してくださいね。
この記事でわかること
- 年3.5%前後の安定した分配金利回りが期待できる
- 月3万円の積立投資で年間1万円超の分配金を狙える
- 楽天証券の新NISA成長投資枠で100円から購入可能
- 定期的な分配金収入で資産形成のモチベーションが続く
目次
結論|楽天SCHDの利回りは年3.5%前後!新NISAで始める将来のじぶん年金づくり

将来のお金の不安を解消するために、「配当金生活」や「不労所得」に興味を持っているなら、楽天証券の「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(愛称:楽天SCHD)」が有力な選択肢です。
楽天SCHDは、米国の優良な高配当企業にまとめて投資できる人気の投資信託で、結論から言うと、税引前で年3.5%前後の安定した分配金利回りが期待できます。
この記事では、楽天SCHDの利回りや具体的なシミュレーション、投資する上での注意点から実際の買い方まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。
この記事でわかること
- 年3.5%前後の安定した分配金利回りが期待できる
- 月3万円の積立投資で年間1万円超の分配金を狙える
- 楽天証券の新NISA成長投資枠で100円から購入可能
- 定期的な分配金収入で資産形成のモチベーションが続く
年3.5%前後の安定した分配金利回りが期待できる
楽天SCHDの分配金利回りは、投資対象である本家ETF「シュワブ・米国配当株式ETF(SCHD)」の実績から見て、税引前で年3.5%前後を期待できます。
投資対象のSCHDが、財務が健全で10年以上連続で配当を支払っている米国の優良企業約100社へ厳選して投資しているため、安定した利回りが狙えるわけです。
実際に、SCHDの過去の配当利回りは3%台で安定しており、さらに過去10年の平均増配率は10%を超えるなど、将来受け取る分配金が増えていくことも十分に期待できるでしょう。
日本の銀行預金の金利がほぼ0%であることを考えると、年3.5%前後の利回りは非常に魅力的と言えます。
月3万円の積立投資で年間1万円超の分配金を狙える
楽天SCHDで期待できる年3.5%の利回りを基に、毎月3万円を積み立てた場合のシミュレーションをしてみましょう。
1年間の投資元本36万円(3万円×12ヶ月)に対して、税引前で年間約12,600円の分配金が受け取れる計算になりますね。
| 積立期間 | 投資元本(累計) | 年間分配金(税引前・目安) |
|---|
| 1年後 | 36万円 | 約12,600円 |
|---|
| 3年後 | 108万円 | 約37,800円 |
|---|
| 5年後 | 180万円 | 約63,000円 |
|---|
| 10年後 | 360万円 | 約126,000円 |
|---|
| 20年後 | 720万円 | 約252,000円 |
|---|
※想定利回り年3.5%で計算した場合。基準価額や分配金の変動、複利効果は考慮していません。
ただし、投資であるため元本保証はなく、基準価額や為替レートの変動で受け取れる金額は変わります。
毎月コツコツ積み立てていけば、受け取れる分配金も雪だるま式に増えていき、将来の年金の足しやちょっとしたお小遣いになるのは間違いありません。
特に新NISA口座を利用すれば、分配金にかかる国内の税金が非課税になるため、より効率的に資産を増やせます。
楽天証券の新NISA成長投資枠で100円から購入可能
楽天SCHDは、楽天証券でしか購入できない専用の投資信託です。
SBI証券やマネックス証券など他の証券会社では取り扱いがない点には注意してくださいね。
購入の際は、2024年から始まった新NISAの「成長投資枠(年間240万円まで)」を利用でき、最低100円からという非常に少額から積立投資を始められます。
「いきなり大きな金額を投資するのは怖い」という投資初心者の方でも、お試し感覚で気軽にスタートできるのは嬉しいポイントです。
定期的な分配金収入で資産形成のモチベーションが続く
投資で資産を増やす上で最も難しいのは、長期的に続けることです。
楽天SCHDの場合、年4回(2月・5月・8月・11月)と3ヶ月ごとに分配金が支払われます。
実際に自分の証券口座にお金が振り込まれる体験は、投資の成果を目に見える形で実感させてくれるでしょう。
値上がり益だけを狙う投資信託と違い、定期的なインカムゲインを得られることは、資産形成を続ける大きなモチベーションになります。
楽天SCHDの利回りに潜む注意点|投資前に知るべき5つのデメリット

年3.5%前後の安定した利回りが期待できる楽天SCHDは非常に魅力的ですが、投資である以上、もちろんリスクやデメリットも存在します。
良い面だけでなく、注意すべき点をしっかり理解した上で、納得して投資を始めることが大切です。
ここでは、楽天SCHDに投資する前に必ず知っておくべき5つのデメリットを解説しましょう。
楽天SCHDのデメリット5選
- 基準価額が下落すると分配金が元本払戻金(タコ足配当)になる
- S&P500などに比べ値上がり益(キャピタルゲイン)は期待しにくい
- 円高が進むと為替差損で基準価額が下落する
- 為替リスクを自身でコントロールしたいならDMM FXも一つの選択肢
- NISA口座で再投資を選ぶと非課税投資枠を消費してしまう
基準価額が下落すると分配金が元本払戻金(タコ足配当)になる
投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金」の2種類があります。
普通分配金は運用で得た利益から支払われるものですが、相場全体の下落などで楽天SCHDの基準価額が購入時より下がった状態で分配金を出す場合、その分配金は利益ではなく元本の一部払い戻し、いわゆる「タコ足配当」となります。
元本払戻金は非課税ですが、実質的に自分の投資した元本が戻ってきているだけなので、手放しでは喜べません。
分配金が出た際には、その内訳が利益から支払われているのか、元本を取り崩しているのかを確認する習慣をつけましょう。
S&P500などに比べ値上がり益(キャピタルゲイン)は期待しにくい
楽天SCHDは、あくまで安定した分配金(インカムゲイン)を得ることを主目的としたファンドです。
そのため、米国の代表的な株価指数であるS&P500や、全世界の株式に投資する「オール・カントリー(オルカン)」といったインデックスファンドに比べると、基準価額自体の大きな値上がり(キャピタルゲイン)は期待しにくいと考えましょう。
過去のパフォーマンスを見ても、トータルリターンではS&P500に連動するファンドの方がSCHDを上回っています。
短期的に大きなリターンを狙うのではなく、長期的に安定した分配金を受け取りながら、緩やかな資産成長を目指すのが楽天SCHDの基本的なスタイルと考えてOKです。
円高が進むと為替差損で基準価額が下落する
楽天SCHDは米国の株式に投資する商品なので、米ドルと日本円の為替レートの変動から直接影響を受けます。
例えば、1ドル150円の時に投資を始め、その後景気変動などで1ドル140円といった円高になると、円に換算した時の資産価値は目減りしてしまいます。
もちろん逆に円安が進めば、円換算での資産価値は増えることになります。
海外資産へ投資する際には、常に為替リスクが伴うことを理解しておく必要がありますね。
為替リスクを自身でコントロールしたいならDMM FXも一つの選択肢
楽天SCHDの為替リスクは避けられませんが、為替の変動をリスクではなく収益機会と捉える投資手法もあります。
為替の変動自体を収益機会と捉える投資手法が、FX(外国為替証拠金取引)です。
FXと聞くと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、最近は初心者でも使いやすいツールが充実しています。
例えば、DMM FXならシンプルで直感的に操作できるスマホアプリがあり、24時間対応のサポートも受けられるので、初めての方でも安心して為替取引を始められます。
円高局面では買い、円安局面では売るといった取引を自分で行うことで、楽天SCHDの為替リスクを相殺(ヘッジ)する、といった戦略も可能になるでしょう。
NISA口座で再投資を選ぶと非課税投資枠を消費してしまう
楽天SCHDの分配金コースには、分配金を受け取る「受取型」と、受け取った分配金で自動的にファンドを買い増す「再投資型」があります。
新NISA口座で「再投資型」を選んだ場合には、注意したい点があります。
再投資される分配金の金額も、年間の非課税投資枠(成長投資枠なら240万円)の一部を消費してしまうのです。
NISAの非課税メリットを最大限に活用したいと考えている方は、再投資される金額も考慮して年間の投資計画を立てる必要がありますね。
楽天SCHDの利回りを最大化する買い方|NISA成長投資枠での積立設定手順

楽天SCHDのメリット・デメリットを理解したところで、いよいよ具体的な購入方法を見ていきましょう。
楽天SCHDは楽天証券でしか購入できませんが、スマホアプリやPCサイトから簡単に積立設定ができます。
ここでは、税金面で最も有利な新NISAの「成長投資枠」を利用した積立設定の手順を、スマホとPCそれぞれで解説します。
NISAでの買い方とコース選択
- スマホで完結!楽天証券アプリでの積立設定7ステップ
- PCでじっくり設定!楽天証券公式サイトでの積立設定7ステップ
- 分配金コースは「受取型」と「再投資型」のどちらを選ぶべきか
スマホで完結!楽天証券アプリでの積立設定7ステップ
多くの方が利用するスマホでの設定は、楽天証券の「iSPEED」アプリを使えば7つのステップで完了します。
通勤時間などのスキマ時間でも手軽に設定できますよ。
スマホでの積立設定手順
- 楽天証券のアプリにログインし、画面下部の「探す」をタップ
- 検索窓に「SCHD」または「米国高配当」と入力し、ファンドを検索
- 「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」をタップ
- ファンド詳細画面で「積立設定」をタップ
- 口座区分で「NISA成長投資枠」を選択し、引落方法(楽天キャッシュや楽天カードなど)と毎月の積立金額を入力
- 分配金コースを「受取型」または「再投資型」から選択
- 目論見書を確認し、取引暗証番号を入力して注文を確定する
PCでじっくり設定!楽天証券公式サイトでの積立設定7ステップ
大きな画面で落ち着いて設定したい方は、PCサイトからの設定がおすすめです。
基本的な流れはスマホアプリと同じで、こちらも7ステップで簡単に設定できます。
PCサイトでの積立設定手順
- 楽天証券の公式サイトにログインし、上部メニューの「投信」をクリック
- 投信スーパーサーチの検索窓に「SCHD」または「米国高配当」と入力
- 検索結果から「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」を選択
- ファンド詳細画面で「積立注文」をクリック
- 口座区分で「NISA成長投資枠」を選択し、引落方法と毎月の積立金額、分配金コースを入力
- ポイント利用の設定を行う
- 目論見書を確認し、取引暗証番号を入力して注文を確定する
分配金コースは「受取型」と「再投資型」のどちらを選ぶべきか
積立設定の際に迷うのが、分配金コースの選択でしょう。
どちらが良いかは、あなたの投資目的によって決まります。
定期的に分配金を受け取って投資の成果を実感したい、お小遣いとして使いたいという方は「受取型」がおすすめです。
一方、分配金を再投資に回して複利効果を最大限に活かし、効率よく資産を増やしていきたい方は「再投資型」を選びましょう。
ただし、楽天証券のNISA口座では一度設定したコースを後から変更することはできないため、最初の設定は慎重に行う必要がありますね。
楽天SCHDの利回りをライバルファンドと比較|SBI・VYMと比べてどれを選ぶべきか

楽天SCHDは非常に魅力的な高配当ファンドですが、投資の世界には他にも似たような選択肢があります。
他のファンドと比較することで、楽天SCHDの特徴がより明確になり、あなたの投資方針に合っているかどうかの判断がしやすくなります。
ここでは、特に比較対象として名前が挙がりやすい「SBI・S・米国高配当株式ファンド」と「楽天・VYM」の2つを取り上げ、楽天SCHDとどこが違うのかを比較してみましょう。
ライバルファンドとの特徴比較
- SBI証券の類似ファンド「SBI・S・米国高配当株式」との違いを比較
- もう一つの人気高配当ETF「楽天・VYM」との違いを比較
- 増配率重視なら楽天SCHD、銘柄の分散性ならVYMがおすすめ
SBI証券の類似ファンド「SBI・S・米国高配当株式」との違いを比較
SBI証券からも、楽天SCHDと全く同じ「SCHD」に投資する投資信託「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」が提供されています。
まさに直接のライバルと言える商品ですね。
| 比較項目 | 楽天・SCHD | SBI・S・米国高配当株式 |
|---|
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 | SBIアセットマネジメント |
|---|
| 投資対象ETF | SCHD | SCHD |
|---|
| 信託報酬(税込) | 年率0.1238%程度 | 年率0.1238%程度 |
|---|
| 主な販売会社 | 楽天証券 | SBI証券 |
|---|
| 決算頻度 | 年4回 | 年4回 |
|---|
| ポイント | 楽天ポイントが貯まる・使える | Vポイントなどが貯まる・使える |
|---|
両ファンドを比較すると、信託報酬はほぼ互角で、どちらも業界最安水準です。
大きな違いは、単純に楽天証券で買うか、SBI証券で買うかという点になります。
すでに楽天証券でNISA口座を開設している方や、楽天ポイントを貯めている方は楽天SCHDを、SBI証券をメインで使っている方はSBIのファンドを選ぶのが自然な流れでしょう。
もう一つの人気高 solchenの人気高配当ETF「楽天・VYM」との違いを比較
楽天証券には、楽天SCHDと並んで人気の高い高配当ファンド「楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)」(愛称:楽天・VYM)があります。
こちらは「バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)」という別の高配当ETFに投資する商品です。
| 比較項目 | 楽天・SCHD | 楽天・VYM |
|---|
| 投資対象ETF | SCHD | VYM |
|---|
| 投資対象の銘柄数 | 約100銘柄(財務健全性などで厳選) | 約400銘柄(幅広く分散) |
|---|
| 分配金利回り(目安) | 約3.5% | 約3.0% |
|---|
| 増配率の傾向 | 高い(連続増配実績を重視) | 安定的 |
|---|
| 構成セクター(上位) | 情報技術、金融、ヘルスケア | 金融、ヘルスケア、生活必需品 |
|---|
| こんな人におすすめ | 将来の増配に期待したい人 | より分散された安定感を求める人 |
|---|
楽天SCHDと楽天・VYMの最大の違いは、投資する銘柄数と構成セクターです。
楽天・VYMが米国の高配当株約400銘柄に幅広く分散投資するのに対し、楽天SCHDは約100銘柄に厳選しています。
また、近年の増配率の高さでは楽天SCHDに軍配が上がりますが、投資先の分散性では楽天・VYMの方が優れていると言えますね。
増配率重視なら楽天SCHD、銘柄の分散性ならVYMがおすすめ
結局のところ、楽天SCHDと楽天・VYMのどちらが良いかは、何を重視するかによります。
将来的に受け取れる分配金が増えていくことを期待し、高い増配率に魅力を感じるなら「楽天SCHD」がおすすめです。
一方、より多くの企業に幅広く分散投資することで、安定感を重視したいという方は「楽天・VYM」を選ぶのが良いでしょう。
どちらも優れた高配当ファンドなので、ご自身の投資スタイルに合った方を選ぶ、あるいは両方に投資してポートフォリオを組むのも面白いかもしれませんね。
楽天SCHDの利回りや分配金に関してよくある質問

最後に、楽天SCHDの利回りや分配金に関してよくある質問に回答します。
よくある質問
- 楽天SCHDの分配金はいつ、いくらもらえますか?
- 楽天SCHDの利回りは、だいたい何%ですか?
- SBI証券やマネックス証券でも楽天SCHDは買えますか?
- NISAで楽天SCHDに投資すると、税金はどうなりますか?
- 楽天SCHDの購入時に手数料はかかりますか?
- 年間30万円の分配金をもらうには、いくら投資が必要ですか?
- 楽天SCHDの基準価額が下がるのはなぜですか?
- 楽天SCHDと楽天・VYMは、結局どちらがおすすめですか?
楽天SCHDの分配金はいつ、いくらもらえますか?
楽天SCHDの分配金は、年4回(2月・5月・8月・11月)の各25日前後に決算が行われ、支払われます。
分配金の金額は決算ごとに変動しますが、直近の実績では1万口あたり70円〜85円程度でした。
実際の入金は、決算日の数営業日後とお考えください。
楽天SCHDの利回りは、だいたい何%ですか?
楽天SCHDの分配金利回りは、税引前の実績ベースで年3.5%前後を目安と考えておくと良いでしょう。
この利回りは、投資対象である本家ETF「SCHD」の過去の実績に基づいています。
ただし、利回りは基準価額の変動によって常に変わるため、あくまで参考値として捉えてくださいね。
SBI証券やマネックス証券でも楽天SCHDは買えますか?
いいえ、「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(楽天SCHD)」は、楽天証券でしか購入できない専用の投資信託です。
SBI証券には非常によく似た「SBI・S・米国高配当株式ファンド」がありますが、これは別の商品です。
楽天SCHDに投資したい場合は、楽天証券の口座開設が必須となります。
NISAで楽天SCHDに投資すると、税金はどうなりますか?
新NISAの成長投資枠を使って楽天SCHDに投資した場合、受け取る分配金にかかる日本国内の税金(20.315%)が非課税になります。
通常の課税口座に比べて、手取り額が多くなるのが大きなメリットです。
ただし、米国での税金(10%)は源泉徴収される点には注意しましょう。
楽天SCHDの購入時に手数料はかかりますか?
楽天SCHDの購入時手数料は無料(ノーロード)です。
ただし、ファンドを保有している期間中は、運用管理費用として信託報酬(年率0.1238%・税込)が毎日かかります。
信託報酬は、投資信託の純資産総額から日々差し引かれています。
年間30万円の分配金をもらうには、いくら投資が必要ですか?
税引後の利回りを2.8%(税引前3.5% × 税金約20%を考慮)と仮定すると、年間30万円の分配金を得るためには約1,071万円の投資元本が必要という計算になります。
あくまで単純計算であり、基準価額や利回りの変動、NISA口座の活用などで必要な金額は変わります。
大きな金額ですが、非課税メリットのあるNISA口座などを活用し、長期的な積立でコツコツと目標を目指すのが現実的です。
楽天SCHDの基準価額が下がるのはなぜですか?
楽天SCHDの基準価額が下がる主な理由は、大きく分けて2つあります。
1つは、投資対象である米国株式市場全体が、景気後退懸念や金利上昇などの影響で下落することです。
もう1つは、米ドルに対して円高が進み、円換算での資産価値が下がることです。
短期的な価格変動は避けられないため、長期的な視点で投資を続けることが大切になります。
楽天SCHDと楽天・VYMは、結局どちらがおすすめですか?
どちらも優れた高配当ファンドですが、投資スタイルによっておすすめが変わります。
将来の分配金の増加に期待する「増配率」を重視するなら、楽天SCHDがおすすめです。
一方、約400銘柄に投資する「分散性の高さ」で安定感を重視したいなら、楽天・VYMを選ぶと良いでしょう。
まとめ|楽天SCHDの利回りは年3.5%が目安!NISAでコツコツ配当金生活を目指そう

今回は、楽天SCHDの利回りや分配金、注意点から具体的な買い方まで解説しました。
楽天SCHDは、年3.5%前後の安定した利回りが期待できる、将来の不労所得作りに最適な投資信託です。
新NISAの非課税メリットを活かし、楽天証券で少額からコツコツ積み立てていくのがおすすめですよ。
楽天SCHD利回りまとめ
- 期待できる分配金利回りは税引前で年3.5%前後
- 投資対象は財務が健全な米国の高配当企業約100社
- 新NISAの成長投資枠を活用して非課税で運用可能
- 楽天証券の専用ファンドで100円から積立投資できる
- 分配金は年4回(2月・5月・8月・11月)
- 基準価額の下落時には元本払戻金(タコ足配当)になるリスクあり
- S&P500などに比べ大きな値上がり益は期待しにくい
- 円高になると為替差損が発生する点に注意
- 分配金コースは「受取型」と「再投資型」から選択
- 増配率を重視するなら楽天SCHD、分散性なら楽天・VYMがおすすめ
楽天SCHDは、将来のお金の不安を「定期的な収入」という形で解消してくれる心強い味方です。
この記事を読んで少しでも興味が湧いたら、まずは楽天証券で口座を開設し、月々1,000円や5,000円といった少額からでも「じぶん年金づくり」の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
コツコツ続ければ、数年後にはきっと大きな成果となって返ってくるでしょう。